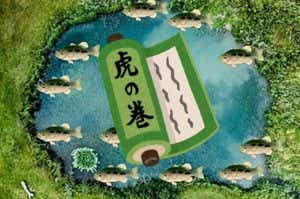釣れないとつい、ルアーを小さくしていませんか?

「今日は活性が低いからライトリグにチェンジ!」というのは、バス釣りの定番のセリフ。巻きモノからライトリグに変更してバスを釣り上げるシーンを、テレビや雑誌でよく見かけますよね。
しかし、満を持してライトリグを投入したものの、「テレビのようには釣れない」ってことはありませんか? そこには、思わぬ落とし穴が潜んでいました。
ライトリグの弱点
一般的に「よく釣れる」とされるライトリグですが、むやみに投入するのは避けたいところ。じつはライトリグにはこんな弱点もあるのです。
①手返しが悪い

速いスピードで広範囲を“線”で探れるハードルアーに対し、ライトリグは1投当たりに費やす時間が長く、“点”でしか魚を誘えません。
魚の密度が濃いエリアならともかく、広いフィールドや魚影が薄い場所では、魚との遭遇率が下がることは明らかです。
②アピール力が弱い

大型のルアーに比べて波動の弱いライトリグは、魚へのアピールが苦手。濁った水質や大きなフィールドでは、魚に気付いてもらえません。
魚を寄せることができないため、目の前にルアーをアプローチしなければ魚に出会えないのです。
③リアクションバイトを誘発できない

ライトリグはナチュラルな波動で、魚の食性に訴えかけるルアーです。そのため、リアクションバイト(反射食い)を誘えません。
エサを探している個体にしか効力を発揮できないため、釣れるタイミングが限られてしまいます。
じゃあ、なぜプロはライトリグで釣れるのか?

プロがライトリグで魚を釣る背景には、一般アングラーとは比べ物にならない実釣時間や経験、張り巡らされた情報網があります。
つまり、魚の居場所を絞り込めているからこそ、ライトリグが効果を発揮するのです。
そのため、ライトリグを有効活用するには、アピールの強いルアーで魚を探すことが必要不可欠。
カメラの回っていないところでは、針を外したプラグを投げて、魚の居場所を探しているプロもいるようです。
ライトリグを投げる前に試したいこと
それでは、思うようにバスが釣れない時は、ライトリグを投げる前になにができるのでしょうか。釣りの原点に立ち返って考えてみました。
場所を変える

魚がいなければ、どんなルアーを投げても魚は釣れません。魚釣りでもっとも大切なことは、“魚がいるところに行くこと”。
そのポイントの良し悪しを判断するためにも、効率よく広範囲をサーチすることが大切です。
時合を待つ

大食いのイメージがあるブラックバスですが、常時エサを求めているわけではありません。食い気がない時は、目の前のエサにすら反応しないことも。
朝夕のマズメや風の吹き始め、雨の降り始めなど、バスが捕食行動に移るタイミングを待つことも必要です。
釣れない時こそ、ルアーを大きく!

釣れない時や、魚の動きを掴みきれない時こそ、魚を探すことが大切です。思い切ってアピールの強いルアーを投入すると、釣果に結び付くかもしれません。
魚との遭遇率を上げて、まずは魚にルアーを見せるところから、釣りが始まります。
▼魚を見失った時に投げたいルアー達
結局のところ、“適材適所”

“適当なスポットに、適当なタイミングで、適用な仕掛けを入れる”ことが、ジャンルを問わず、釣りの鉄則。
時には、定説や過去の経験が裏目に出ることもあります。目の前のフィールドと向き合うことが、釣果への早道でしょう。