本記事で使用されている画像の一部は、画像生成AIを使用して生成されたものでありフィクションです。登場する人物、団体、名称、場所などはすべて架空のものであり、実在するものとは一切関係ありません。
“バス”ではなく“人”から教わった人たちへ(私も含め)

「〇〇というルアーは、じつは〇〇の動きを再現している」
——そんな説明を、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
けれど、私たちが語る“ルアー論”の多くは、自分の体験からではなく、師匠やプロ、あるいはメディアから借りてきた言葉にすぎません。(※借りてない方はごめんなさい)
そして、その“発信元”は——人間であって、バスではありません。
冷静に考えてみれば、それが本当かどうかなんて、バスでない私たちに分かるはずもないのです。
だけどせっかくです。もう一度、考えてみませんか?
——どう考えても餌に見えないルアーを、バスはいったい何と勘違いしているのか。

uoppay
ちなみに、私は「このルアーはバスにはこう見えている」などと、詐欺師のような断言をするつもりはありません。
ただ、もう一度“考えるきっかけ”を差し出したいだけなのです。
ラバージグをザリガニだと信じた少年時代

「おったなぁ!」「電撃フッキングや!」「これがスキッピングっていうんだぜ!」
約30年前、テレビの中のプロアングラーたちはまるでヒーローでした。
彼らに憧れ、私はラバージグというルアーに夢中になりました。

雑誌を開けば、「ラバージグは、ザリガニが爪を立てて威嚇する姿を模している」と書かれていました。
たしかに、みんなザリガニ型のワームをトレーラーにしていましたし、爪の形をしていなくても、ワームやポークのパーツは必ず二対に分かれていました。

uoppay
だから私は、ラバージグ=ザリガニという図式を、疑うことなく信じ込んでいたのです。
トレーラーを付けないほうが釣れる……だと?

ところがある日、私の“常識(思い込み)”はあっけなく崩れました。
ザリガニとは似ても似つかない「スモールラバージグ」なるルアーが登場したのです。
当時、「何だこれは?」と思ったアングラーは、きっと私だけではなかったはずです。

その後、ラバージグはスカートの量やカラーも多様化していきました。
トレーラーワームも、シングルテール、シャッドテール、ギル系、巨大なポーク……。
その姿を変えながら、流行もまた移り変わっていきました。
極めつけは、某プロの「トレーラーを付けないほうが釣れる」という一言。
フルサイズのラバージグにザリガニ系ワームを付けることにロマンすら感じていた私にとって、それは世界がひっくり返るような出来事でした。

uoppay
——ですが、私のロマンなど、バスにとってはどうでもいい話です。
「釣れる」という事実は変わらない

ただ結局のところ、ラバージグは釣れる。
そして、どんなトレーラーでも、トレーラーを付けていなくても釣れる。
その「釣れる」という事実が変わらないことこそが重要なのです。
そしてもう一つ、確かに残った気づきがあります。
ラバージグとは、細長い複数のラバーが巻かれたルアー。
その細い束が、水中でふわりと揺らめき、形を変えていく——。
私が言いたいのは、その“変わり続ける動き”そのものに、バスは生命を感じているのかもしれないということです。

uoppay
バスはきっと、「ラバーの動き」を見ている。
「餌っぽい」「生き物っぽい」とは何なのか

次に、「餌っぽい」「生き物っぽい」という言葉について考えてみましょう。
現存するあらゆる生き物やルアーの中で、最も“生き物に近いもの”とは何でしょうか。当然のことながら——本物の生き物ですよね。
では、その次に“生き物に近いもの”は何でしょうか。
ここで思い出してほしいのが、死に餌の存在です。
ブラックバスを餌で狙うとき、生き餌と死に餌ではどちらが釣れると思いますか?
もちろん状況にもよりますが、私の知る限り、確実に生き餌のほうが釣れます。

uoppay
人間にとっては、むしろ死んだ魚のほうが食べやすいのに——彼らはなぜ、わざわざ生きた餌を好む(選ぶ)のか?
彼らにとってのレギュラーとは

おそらく、彼らにとって「生きている餌を食べる」ことがレギュラーであり、「死んだ餌を食べる」ことがイレギュラーなのではないでしょうか。
水中を見渡せばわかるように——生きて動くものと、死んで静止したものでは、遭遇する頻度も印象もまるで違います。
いつも目にするのは、ゆらぎ、泳ぎ、逃げ、震える“動いている側”。それこそが、彼らにとっての日常です。
つまり、たとえそれが本物の死体であっても、バスにとっては異質な存在。
だからこそ、「生きているものに近づける」ことは、彼らのレギュラーに寄せることであり、釣る確率を高めるための、もっとも自然なアプローチと言えるのです。

uoppay
付け加えるなら、バスにとって危険が少なく、確実に食べられそうな「生きているものに近づける」と、もっと釣れる気がします。
生きているものと死んでいるものの決定的な違い

では、生きているものと死んでいるものの決定的な違いとは何でしょうか。
それは、動いているかどうかです。
生きているものは、まず移動します。そして呼吸をし、揺れ、たわみ、形を変えます。
死んでいるものは、硬直し、変化を失います。
——つまり、“動き”こそが、“生き物らしさ”の正体なのです。

uoppay
ここでようやく、トレーラーワームのない、ただのラバージグが釣れる理由と繋がったような気がしませんか?
ワームは生き物らしさを容易に演出できる

ワームの実力は、ご存知の通り。
では、なぜ“釣れる”のか——今一度、考えてみましょう。
揺れ、たわみ、形の変化。それらは“生き物らしさ”を形づくるうえで、極めて重要な要素です。
そして、それを誰でも手軽に演出できるのが、ワームなのです。
ワームは、その名のとおり柔らかい素材でできており、形を自在に変化させます。
アングラーがアクションを加えなくても、ワームは水流に合わせて形を変え、揺らめき、
ときに地形の傾斜に沿って転がっていく。
——それこそが、ワーム最大の強みなのです。

悲しいかな、バスやニジマスのお腹からワームが出てくることがあります。
もちろん、ラインブレイクが原因のこともあるでしょう。
ですが、多くは——水中で放置されたワームを、魚が“生きている”と勘違いして飲み込んでしまった結果かもしれません。

uoppay
ただし、「ワームを飲み込んだ魚をよく見る」というのは、“ハードルアーを飲み込んだ魚が、そもそも生きていない”だけ——
そんな観測バイアスの可能性も捨てられませんので、早合点は禁物です。
ハードルアーにも、生き物らしさがある

生き物らしさは、ラバーやワームのように“形の変化”だけで完結するものではありません。
たとえば、ハードルアー。ワームのように形は変わらないのに、ちゃんと釣れる。
それは、ハードルアーが魔法だから——そうファンタジーに包んでおくのも一興ですが、要するに、“ハードルアーにも生き物らしさが内包されている”ということではないでしょうか。

クランクベイトも、バイブレーションも、スピナーベイトも——見た目だけ見れば、どう考えても生き物とは程遠い。
それでも釣れるのは、“横方向の動き”という、小魚に通じる挙動を備えているからです。
ただし、多くの方が感じているように、ハードルアーってなかなか釣れませんよね。
形の変化がないうえに、剥き出しの針など——バスに警戒心を与える“異物感の塊”だからです。
だからこそ、“濁り”など異物感を誤魔化せる舞台や、スピード等の演出が加わってこそ輝く。

uoppay
もしルアーをレーダーチャートで表すなら、ハードルアーはひとつの能力を極限まで尖らせた“1点特化型”。
当然、使い所や使い手を選ぶのです。
何に見えているかの前に、彼らの精神の話をしよう

動き、異物感を消す舞台、そして演出。
——ここまでで、「どう見ても餌に見えないルアーでも釣れる理由」が、少し見えてきたと思います。
ですが、もうひとつ忘れてはならない要素があります。
それは、バスの“精神状態”です。
バスがいつも冷静だと思ったら、大間違い。
産卵期や荒天前後など、わずかな条件の変化で、彼らの行動は一変します。
冷静な個体と、興奮した個体とでは、“食うボーダーライン”がまったく違う。
たとえば、10%程度の生き物っぽさしかないルアーを食べてしまう、狂ったようなタイミングもあれば、100%の生き餌ですら、警戒して食べないことだってあるのです。

「本物のセミを見切るのに、ルアーなんかで釣れるわけないじゃん」
これは、バスがまったく釣れないときの知人の口癖(という名の言い訳)なんですが、どうやら、あながち作り話でもないらしいんです。
これは、ルアーが「何に見えているか」以上に、本質的な問題です。
バスが“冷静でないタイミング”。
ルアーという“偽物”でバスを騙そうとしている以上、そんな日(タイミング)を、どれだけ知っているかが、釣果を分ける大きな要素になりそうです。

uoppay
とはいえ、私自身、引き出しはそれほど多くありません。
しかも、そういう“爆発的に釣れる日”に限って、家で映画を観たり、コタツでぬくぬくしていたいタイプなのが悩ましいところです。
生き物か、それ以外か

最初にサイコロラバーやコイケを見たとき、スモラバを初めて知ったあの瞬間と同じ衝撃が走りました。
そして同時に、どこかで見たような既視感もあったのです。
シルエットが曖昧で、毛がゆらゆらと揺れる——その点は、スモラバとよく似ています。
さらに、ジグヘッドがなく、中心には半透明のワームがあることで、輪郭はいっそうぼやけ、フォールスピードも極端に遅くなる。
いわば、“重力からほんの少し解き放たれたスモラバ”と言えるかもしれません。

では、そのスモラバを——バスは何だと思って食べているのでしょうか。
彼らはきっと、“生き物っぽい何か”だと見なしてはいる。
けれど、それが何であるかという確信までは持てないのではないでしょうか。
たとえば、エビの新種・ヤゴの親戚・やけに毛深いゴリ。
……まあ、毛深いゴリはさておき、彼らの認識はそのくらいの感覚なのだと思います。

バスは、人や学者のように「これはスジエビ、これは手長エビ」と識別しているわけではなく、ただ、“生き物っぽい何か”として認識しているだけ。

uoppay
そして——その“っぽさ”こそが、彼らを騙すための最初の取っ掛かりであり、大前提なのです。
ルアーは、きっと何にでもなる

ルアーを“生き物っぽい何か”に近づけるのは大前提。
さらに言えば、その“生き物っぽさ”が、彼らの普段食べているものに近ければ近いほど、それは彼らにとっての“レギュラー”や“確信”となる(つまり、より釣れる)——。
私は、そう考えています。

ラバージグは、きっと“何にでもなれる”。
ザリガニの多い池でズル引きやボトムバンプをすれば、ザリガニだと思って食ってくる瞬間もあるでしょう。
そして、ギルにも、アユにも、ハスにも、テナガエビにも、カエルにだってなり得る。
ただ、ラバージグであることで、“普段からそこにいるような”生き物っぽさを損ねている状況だってある。
だからこそ、さまざまなルアーが存在し、その時々で輝くルアーが違うのです。
ルアーが“何に見えているか”は、状況によっても、使い方によっても、いくらでも変わる。

uoppay
その“無限の可能性”に悩まされることこそ、釣りの面白さなのかもしれません。
ただの電柱も警官になる

夜道で見かける、反射板を貼った“おまわりさんの形の看板”。
あれを本物の警官だと思って、思わず減速した経験、ありませんか?
あれは、人間が“印象”で世界を補って見てしまう、その心理をうまく突いた錯覚です。
けれど、昼間に見れば、あれを警官だと思う人はいないでしょう。
では、あなたが今キャストしようとしているそのルアー。
それは、昼間の看板になってはいないでしょうか。

uoppay
ただの電柱が、人に見えることだってある。
そう考えれば、どう見ても餌に見えないルアーを魚が勘違いして食べてしまう瞬間があるのも、不思議なことではありません。
で、結局、バスには何に見えているのか?
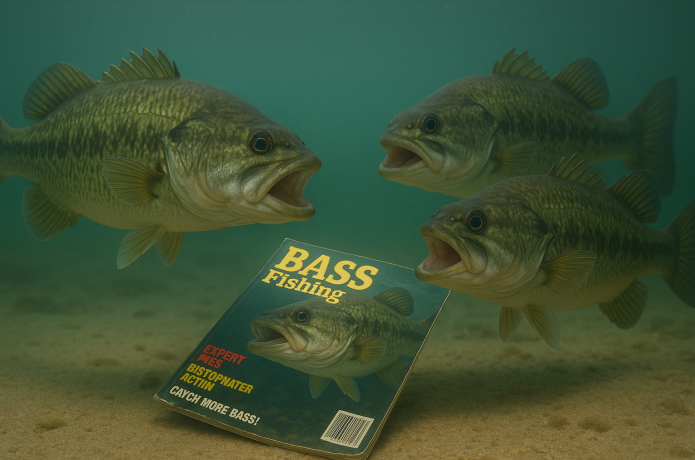
……それは、もう最初に言いましたよね。
私は、「このルアーはバスにはこう見えている」などと、詐欺師のような断言はしません。
人間の世界では、“言い切れる人(ビッグマウス)”ほど信頼され、影響力を持ちやすいものです。
けれど、私たちの狙っているのは——ラージマウスです。
本当に耳を傾けるべきは、人の声ではなく、バスの声。

uoppay
さあ、フィールドに出向き、バスの声を聞きましょう。
そして最後に、小話を

アメリカザリガニやブルーギル——昔に比べて、減ったと思うのは私だけでしょうか。
かの有名な日本一のフィールドでも、メイン(釣れ筋)パターンが、ギルからワカサギに移行したと聞きます。
“レギュラー”とは、時代とともに姿を変えていくものです。
かつて私が憧れた、フルサイズジグにザリガニのトレーラーワーム。
その活躍の声が減ったように感じるのは、もちろんトレンドの影響もあるでしょう。
けれど、もしかすると——フィールドそのものの変化が関係しているのかもしれません。

uoppay
ルアーを“イレギュラー”から“レギュラー”へ。
どう見ても餌に見えないそれを“餌”として成立させていくこと——それは、思考を止めていては決して成し得ない、途方もなく骨の折れる作業なのです。
けれど、その不確かさの中にこそ、釣りという行為の永遠があるのだと思います。
出典表記のない画像撮影:uoppay









