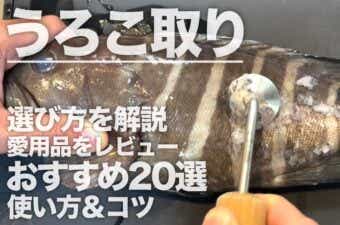ウロコ取りの代用品おすすめ5選

知人の家に行ったときや釣ってすぐに魚を食べたいときに、「ウロコ取りがない!」なんて経験はありませんか?
今回は、元料理人でもある筆者が「これならウロコ取りとして使える」と感じたアイテムを紹介します。

山下
超定番のあのアイテムから、と〜っても意外なアイテムまで。
それぞれの使い分けについても解説していきます!
その1:ペットボトルのキャップ

ペットボトルのキャップは、SNSやYouTubeでもよく紹介される定番の代用品。
身近にあり、手に入りやすいのが魅力です。

使い方は、尾から頭に向けて軽くこするだけ。
角度を浅めに保ち、力を入れすぎないのがきれいに取るコツです。

アジやイワシ、サバなどの小型魚にぴったりで、細かいうろこもよく落ちます。
釣り場で手軽に使えるのも大きなメリットです。

ただし、ペットボトルのキャップはサイズが小さいため、ヒレの長い魚には注意が必要です。
うっかり触れるとケガをすることがあるので、尾ビレや背ビレには触れないようにしましょう。
また、プラスチック製なので、硬いうろこを持つ魚にはやや不向きです。
その2:スプーン

家庭にあるスプーンも、ウロコ取りの代用品としてとても優秀。
使い方は、スプーンの縁を尾から頭に向けて、押し当てずに撫でるように動かします。
金属製のステンレススプーンなら硬さもあり、細かいうろこもきれいに取れます。

メバルやカサゴなど、背ビレや胸ビレの棘が長い魚にもおすすめです。
持ち手に長さがあるため、ヒレを避けながら安全に作業できるのが大きなメリット。

クロダイのようにうろこの硬い魚でも、多少力を入れればしっかりと作業できます。

さらに、スプーンは先端が細く、細かな部分の作業もしやすいのが特徴です。
ティースプーンのような小型スプーンは小魚向きで、カレースプーンは中型魚に最適です。
魚の大きさに合わせてスプーンを使い分けると、より効率良くうろこを落とせます。

ただし、力を入れすぎると皮が剥がれたり、身を削ってしまうこともあります。
うろこだけ落とすように、軽い力で作業しましょう。

また、コンビニやスーパーでお弁当を買ったときにもらえるプラスチック製スプーンも意外と便利。
柔軟性があるためか、うろこが飛び散りにくく、皮を傷つけにくいのが特徴です。
使うときは、スプーンの持ち手と動かす方向が並行になるようにすると、よりきれいにうろこを落とせます。
その3:包丁

魚をさばくのに欠かせない包丁は、家庭に必ず1本はある道具。
ウロコ取りがないときでも、しっかり活躍してくれる代用品です。
包丁に慣れている人なら、専用のウロコ取りとほぼ同じ仕上がりが期待できます。

使うのは、刃の根元から中ほどの部分。
刃先を少し寝かせ、尾から頭に向かって軽くこすり上げるように動かします。

また、ヒレの付け根や頭付近といった細かな部分は、刃先を使うときれいにうろこが取れます。
ただし、硬いうろこを刃先で取ろうとすると、刃が欠ける可能性があるので注意が必要です。

出刃包丁であれば、クロダイのようにうろこが硬く厚い魚でも問題なく作業できます。
牛刀や三徳包丁であっても、アジやシロギスのような小魚なら楽々。
ただし、角度を誤ると皮や身を削ってしまう可能性があるのが注意点。
刃を立てすぎず、表面を撫でるように使うのがポイントです。

うろこが飛び散りやすいので、ビニール袋に魚を入れて作業をするのもおすすめです。

また、刃にうろこが付着したまま放置すると乾燥して固着し、取れにくくなります。
作業後はなるべく早く洗い流し、水気をしっかり拭き取るようにしましょう。
その4:金たわし

昔ながらの掃除道具である金たわしも、ウロコ取りの代用品として活躍。
最近では常備している家庭は少ないものの、アルミ鍋など金属製の調理器具を磨くために使っている人もいます。

使い方は、魚の表面をやさしくこするだけ。
力を入れすぎず、滑らせるように動かすと皮を傷めにくく、均等にうろこが取れます。
また、魚のぬめりも一緒に取れるのも特徴です。

写真ではカサゴに使用していますが、大型の青物やヒラメ、根魚など、うろこが細かく密集している魚と相性抜群。
金属の細い線がうろこの隙間に入り込み、効率良く落とせます。
とくに青物のようにうろこが薄く密集している魚は、たわしの細い線がぴったりフィット。
ウロコ取りを持っている人でも、あえて金たわしを使う人がいるほどです。

注意したいのは、金属部分の「目の粗さ」。
粗いタイプを使うと皮まで削れてしまうことがあります。
また、ヒレの根元など細かい部分までは入り込みにくいため、スプーンと併用すると効率的です。

使用後は、たわしにうろこが残りやすいため、すぐに水でよく洗いましょう。
放置すると乾いて固着し、つぎに使うときの臭いやサビの原因になります。
長期間使わない場合は破棄し、使い捨てにするのがおすすめです。
その5:ピーラーグローブ

100円ショップなどでも手に入るピーラーグローブ。
手袋の表面に細かな凹凸があり、魚をこするだけでうろこを取り除けます。

使い方は、指で尾から頭に向けて表面を撫でるようにするだけ。
うろこが細かく密集した魚でも、短時間で難なく作業が完了。
特別な道具を使わないため、釣り場やアウトドア調理でも活躍してくれます。

凹凸は小さいため、うろこが細かい魚との相性が抜群。
アジ、カサゴ、メバルなどの魚では、きれいにうろこを落とせます。
軽い力で作業でき、うろこが飛び散りにくい点も魅力です。

使用後はうろこが凹凸に残りやすいので、しっかり水洗いして陰干ししましょう。
乾燥が不十分だと、臭いやカビの原因になることがあります。
弱点を理解して使い分けることが重要

ウロコ取り専用の道具がなくても、魚の種類に合わせて代用品を選べば十分に対応できます。
ポイントは、それぞれの得意分野と苦手分野を把握すること。
小型魚には柔らかく当たるもの、硬いうろこの魚には力を伝えやすいもの、ヒレが鋭い魚には安全に操作できるもの——。
このように「魚の特徴 × 作業環境」で使い分けることで、仕上がりが格段に良くなります。
下の表では、筆者が実際に試して感じた相性をまとめました。
| 代用品 | 向いている魚 | 特徴 |
|---|---|---|
| ペットボトルのキャップ | シロギス、アジ、カマスなどの小型魚 | 手軽で扱いやすい。柔らかいうろこ向き。ヒレが長い魚は注意。 |
| スプーン | カサゴ、メバル、マダイなどの中小型魚 | 先端が細く細部の処理が得意。ヒレを避けて安全に使える。 |
| 包丁 | マダイ、アジ、ブリ、カサゴなど幅広い魚種 | 汎用性が高く、角度を工夫すれば小型~大型まで対応可能。 |
| 金たわし | 青物、ヒラメ、根魚など細かいうろこを持つ魚 | 広範囲を素早く処理。柔らかいタイプを選ぶと安心。 |
| ピーラーグローブ | アジ、メバル、カサゴなど、うろこが簡単に取れる魚 | 凹凸が小さく、細かいうろこに最適。軽い力で安全に使える。 |
代用品でも十分にウロコ取りができます!

専用のウロコ取りにはやや劣るものの、魚種に合わせて選べば、代用品でも十分にうろこを取り除けます。
ウロコ取りがなくて困っているときには本記事を読み直し、参考にしながら代用品を探してみてください!
撮影:山下洋太