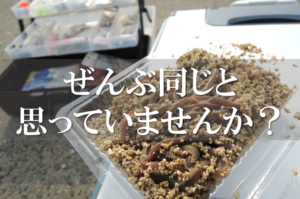ニベについて

ニベは頭部に比較的大きな炭酸カルシウムの結晶である耳石を持つ事から、同じくニベ科のシログチと共にイシモチ(石持ち)と呼ばれます。
昔は魚の浮き袋を「へ」と呼び、ニベの浮き袋を煮てニカワを作った事から「煮へ」が転じて「ニベ」と名付けられました。ニベの浮き袋から作ったニカワは大変粘り気が強く「ニベにもない」という言葉のニベはこの種の魚のニベを指します。
ニベは大変大きな浮き袋を持っており、釣り上げられた時などに浮き袋を使って「グゥグゥ」音を出す事が出来、釣り上げられた不満を愚痴っているようにも見えるため「グチ」とも呼ばれます。
ニベの分布・生息域
ニベは太平洋側では宮城県松島湾以南、日本海側では新潟県以南から東シナ海に掛けての外洋に面した沿岸部に広く分布しており、水深の比較的浅い砂泥底の底層に生息しています。
ニベの性質
ニベは砂泥に生息しているので、海底のゴカイやイソメなどの多毛類の虫やカニ、貝類、小魚を好んで捕食し、夜間や水の濁った状況で活性があがることが多い特徴をもちます。基本的に群れで生活していて底引き網漁で水揚げされる他、カレイ釣り等で外道として釣られます。
ニベの地方名
ニベは漢字で魚へんに免と書きますが、日本各地で同科異属の魚がニベと呼ばれています。代用的なものとしては和歌山・神戸・広島など瀬戸内海地方でニベと呼ばれる魚はコイチで、本来のニベがコイチと呼ばれています。長崎ではクログチと呼ばれますがニベ科クログチ属の魚と混同されています。静岡・高知などではグチと呼ばれます。
ニベの美味しい食べ方は?

ニベは高級蒲鉾の材料として代表的な魚ですが、新鮮な物は鯛の代用として用いられるほど上品な味をしています。身は淡白な白身で締まってますが熱を通すとホッコリと柔らかくなります。脂肪は少なく癖もないので色々な料理に適しています。また皮に旨みと独特な風味があります。
塩焼き
鱗は剥がれやすいので、包丁の背を使って鱗を剥がし内臓を取って塩焼きにします。ニベの塩焼きは、皮目になんとも言えない風味があり身の柔らかくほぐし安く食べやすい魚です。
ムニエル
ニベは脂肪の少ない身質から、油のりが良くムニエルや中華料理にも適しています。塩コショウをして小麦粉を付け油で油でソテーしバターやソースで味を調えれば完成です。皮目に旨味があるので皮をかりっと仕上げるのが良いでしょう。
焼霜造り
新鮮なニベはお造りにしても定評のある魚ですが、皮を剥かずに皮を火であぶった後よく冷やし適当な大きさに切れば完成です。程よい甘さがあり大変美味しいです。
天ぷら
ニベは油のりの良い魚ですので、揚げ物にも向いています。適当な大きさに切り衣を付けて油で揚げれば完成です。白身魚で身も柔らかくほんのりと甘さもある魚なのでお好みで塩でお召し上がりください。
煮付け
一尾のまま身に二箇所ほど切れ込みを入れ煮付けます。煮付けても身は固くならず繊維質で身もほぐし易く食べやすくなります。煮付けても上品でしっとりとした甘味は醤油などのに味負けしません。
ニベとイシモチはどう違う
ニベもイシモチと呼ばれますが、一般にイシモチと呼ばれる魚は同じニベ科のシログチの事を指します。共にイシモチと呼ばれたり、ニベが地方によってグチと呼ばれたり同種が混同されがちですが、ニベはニベ科ニベ属でシログチはニベ科シログチ属になります。
両者の外見上の違いはシログチは鰓上部に境界不明瞭な黒い班があり、背は白く生きている間は七色の光沢があるのでシログチと呼ばれます。一方ニベは鰓上部に黒班はなく背には側線に沿って黒い小点が規則正しく並んでおり全体に黒っぽく見えるます。
ニベは刺身でも美味しい魚

ニベは一般にはまだまだ知名度が低く安価な魚ですが、練り物の材料や火を通しての調理だけでなく刺身にしても相当な旨味を発揮する魚です。新鮮なニベの刺身はモチっとした触感があり、上品で癖もなくあっさりとしほんのりと甘さが有ります。新鮮なニベの刺身を食べる時は釣り上げた後、神経締めするのがお勧めです。
ニベの旬は夏!
ニベは日本近海では通年で釣れる魚ですが、5月~8月に産卵期がありその頃になると産卵の為に体力を蓄えようと荒食いを始めます。そのためニベ釣りのシーズンは産卵期の初夏と言う事になります。産卵を控え体力を蓄えたニベは脂が乗り旨味が増まします。この時期のニベの刺身は鯛をも凌ぐといわれています。中々流通に乗らない魚ですので新鮮なニベは刺身で戴くのをお勧めします。
まとめ
クセのない白身で塩焼きが絶品のニベ。濁りを好む習性があるので、投げ釣りで狙うなら雨の日の翌日や夜釣りで狙ってみましょう。




 出典:PIXTA
出典:PIXTA