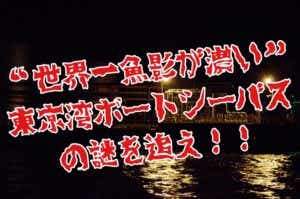ルアー選びはミノーから

前回はシーバスを狙うためのポイント選びについて解説しましたが、今回は「ルアー」について。
毎年多くのルアーが発売され、シーバス用ルアーは数えきれないほど存在しています。
何を選べばいいか分からない……。そんな場合は、登板機会が多くオートマチックに泳いでくれる“ミノー”から選んでみましょう。
筆者の紹介

内田聖、愛知県在住。ライターネームはウッチーダ。
仕事・家庭・釣りと3足のわらじを履いて、日々奮闘中のサラリーマンアングラーです。
APIA、BlueBlueのフィールドテスターを兼任。メインターゲットはシーバス。最近はクロダイやメバルといったターゲット魚種も増え、ソルトルアーフィッシング全般を楽しんでいます。
TSURIHACKではHowtoや最新の釣り動向、時には編集部の無茶ぶりをテーマに、楽しく・わかりやすく執筆していきますよ!
2つの要素を主軸にする

ミノーは顎の部分に「リップ」と呼ばれる水を噛むための板がついており、ルアーを引っ張るだけでリップが水を噛み、ボディを揺らして泳ぎます。
このリップが作用し、同一のレンジを規則的なアクションで泳ぐことが強みなのです。
このため、ミノーを選ぶ際には潜行レンジとアクションに注目して選ぶ必要があります。
潜行レンジ
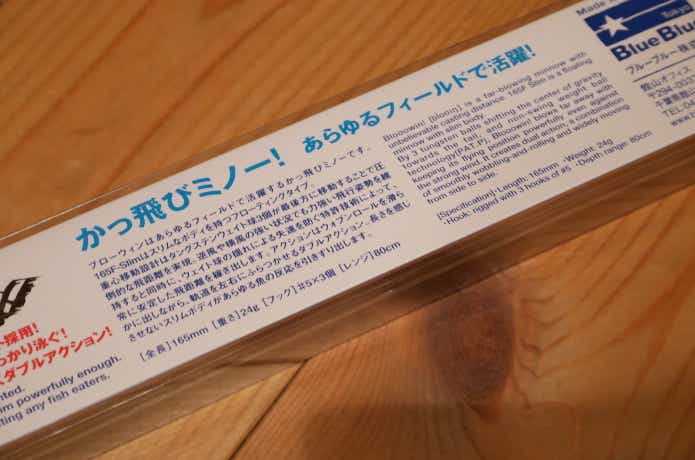
ミノーを水の中に置いた時に浮くものをフローティング、沈むものをシンキングと呼びます。
ルアーの潜行レンジはルアーの比重やリップの長さよって決まりますが、慣れるまでは物を見て判断することは難しいでしょう。
そんな場合はパッケージに記載されている潜行レンジを参照しましょう。
潜行レンジはどう選ぶ?
フィールドで捕食されているベイトの泳ぐ層に合わせ、潜行レンジを選ぶ必要があります。
判断が難しい場合は、潜行レンジが30、60、90センチ前後のものを揃えておくと、相互でカバーしやすいですよ。
フィールドでの選び方

とはいえ、【このベイト=このレンジ】といった決めつけはよくありません。
例えばベイトが「イナッコ」でも、潮位・水温といった状況次第で、泳いでいる層が表層だったりボトムだったりと、異なることもあるのです。
ベイトのレンジを外さないよう、状況に沿ったミノーローテーションを行いましょう。
特に初場所や慣れないときほど、上から探るという意識が重要ですよ。
アクション

レンジだけでなく、ミノーのアクションはリップの横幅で変わります。
リップの幅が広い程、ウォブリングという左右方向に揺れるアクションが強くなります。
また、リップの幅が狭い程、ローリングという回転方向のアクションが強くなり、ボディからのフラッシングで周囲にアピールする事ができます。
両方のアクションも持つ場合、ウォブンロールと表現されることがありますね。
ウォブリングとローリングの使い分け
ウォブリングはアクションが強く水を動かす量が多いため、広い範囲にアピールする事ができる反面、ルアーを見切られやすいという欠点があります。
反対にローリングはアクションがよりナチュラルで見切られにくく、アピール範囲は狭いと言えます。
但し、デイゲームでフラッシングを用いた攻略をする場合は、上下方向に光の反射を飛ばせるローリングのアクションが適していますよ。
巻くミノーと巻かないミノー
アクションは最も重要な部分なので、少し掘り下げましょう。
私の場合は、ウォブリングが強いものをを「巻くミノー」、ローリングが強いものを「巻かないミノー」といったイメージで使い分けています。
私がシーバスを狙う際ミノーの使い分けで、特に強く意識している部分です。
巻くミノー

リップが大きめのウォブリング寄りのルアーは「巻くミノー」と称しています。
リトリーブする事で周囲の水を動かしてシーバスに気づかせ、追いかけさせるルアーですね。
流れの弱いエリアだったり、岸際やストラクチャー(構造物)周りで追い込まれる魚、逃げ惑う魚を意識して使う事が多いです。
リトリーブを一瞬止めて、またすぐ巻き始める“ストップ&ゴー”もこの部類のルアーの得意技。
スレていない魚に強いため、ボートシーバスのバース撃ちなどにも良く使われます。
巻かないミノー

一方リップが小さくローリング寄りで水押しの弱いルアーは「巻かないミノー」と呼んでいます。
“巻かない”とはありますが、実際にはデッドスロー域などのリトリーブ調整で、ミノーを浮遊させるように流れにのせるという意味合いです。
私の場合、大きいシーバスは「巻かないミノー」で釣れる事が多いですね。
これは、大きい個体ほど、小魚を追い回して捕食するというより流れを利用して楽に捕食する、という事だと認識しています。
潮位変化によって流れも変化するため、ミノーも1種類だけだと獲り切れない魚もいるのです。
まずは定番ミノーを使ってみよう

ミノーは潜行レンジやアクションによって細分化され、各メーカーから発売されている物を合わせると、膨大な数のものが発売されています。
そのため、「選択肢が広い」と言うこともできますが、「どれを選べばいいか分かりにくい」というのも実状です。
そんな時は、誰しもが使いやすい“定番”といわれるミノーを選択するといいでしょう。使いやすさだけでなく、やはり定番と言われるだけの良さがあります。
EXSENCE Silent Assassin129F AR-C

潜行レンジは50~80センチ、アクションはウォブンロール。サイズはおよそ130ミリと少し大きめです。
外洋絡みのエリアや、メインベイトのサイズが大きいエリアではスタンダードなサイズと言えるでしょう。
このサイレントアサシン129Fですが、AR-C機構により非常に優れた飛距離を持つルアーです。
ボディに対しリップは小さめ。比較的弱いアクションを持ち、ファットなボディでしっかり浮力を持っているので、ナチュラルにアクションしてくれます。
私の印象としては、ルアーサイズが大きい割に小型のシーバスもどんどんバイトしてくるので、それだけ集魚力と喰わせ力の高いミノーと認識しています。
サイレントアサシン 129F
DOVER99F

港湾でも河川でも磯でも使いやすい汎用的なフローティングミノーです。
潜行レンジは60~90センチ、アクションはウォブンロール。リトリーブスピードを弱めれば30センチのレンジを狙うのも容易です。
サイズもおよそ100ミリとベイトのサイズを考えれば、オールラウンドに使用できますね。
私の場合、潜行レンジの相性から1投目で選択することが多いです。
ドーバー 99F
簡単なルアーだからこそ

最初にも記載したように、一定のアクションで同じレンジを狙うルアーがミノー。ルアーの中でもオートマチックに魚を狙えるルアーです。
それだけに、アクションやレンジを“どこに合わせるか”が重要となってきます。
そして、自分なりに工夫してミノーを使い分けることで、ルアーローテーションの精度も上がり、戦略を伴ったミノーの選択ができるようになりますよ。