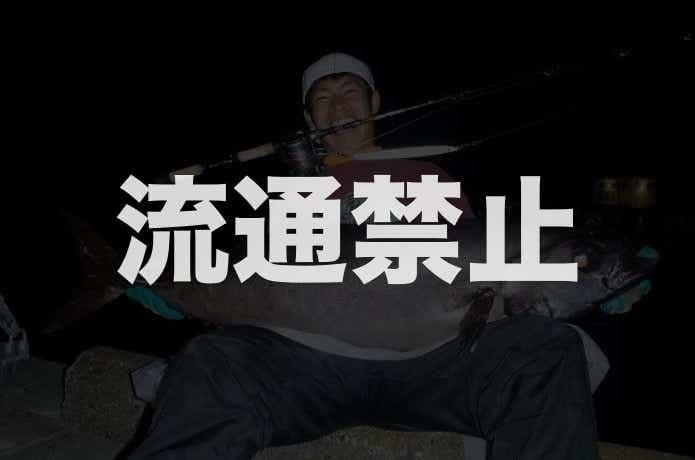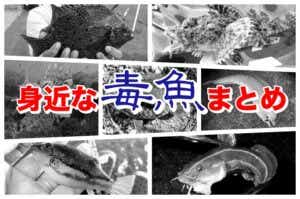流通させてはいけない魚

この地球には3万6千を超える多種多様な魚たちが棲息しています。
ご存知の通り、すべての魚が美味しく食べられるわけではなく、中には人の命を奪ってしまう猛毒を持つ魚も。
今回の記事では、食品衛生法第6条第2号によって、日本において食品としての流通が禁止されている魚をご紹介します。
食品衛生法第6条第2号
有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
フグ類(定められた種類および部位以外禁止)
有毒成分|テトロドトキシン

毒魚と聞いて真っ先に思い浮かぶ魚といえば、フグの仲間でしょう。
フグ毒とも呼ばれる「テトロドトキシン」の致死量は0.5~3mg、じつに青酸カリの約1,000倍の強さとされています。
マフグの肝臓1つで32人、トラフグの卵巣で12人の命を奪うだけの毒量があるのです。
種類によって毒がある部位が異なる

猛毒を持つフグですが、日本人にとっては高級食材という一面も。
フグは種類によって毒を持つ部位が異なるため、有資格者が種を同定した上で、定められた施設で正しく調理することによって安全に食べられます。
有毒部位を含んだ状態での一般消費者への販売は、法律で禁止されています。
フグ毒による患者数と死者数について

フグ毒を原因とする食中毒は毎年発生しています。
食後20分から3時間程度でしびれや麻痺症状が現れ、重症化すると呼吸困難によって死亡。
平成26年から令和5年までの10年間に、フグ中毒の患者数は235名、死者数は5名が記録されています。
バラムツおよびアブラソコムツ(流通禁止)
有毒成分|ワックス

バラムツとアブラソコムツの筋肉には、ヒトが消化吸収できないワックスエステルが多く含まれています。
主な中毒症状は下痢であり、バラムツは1971年に、アブラソコムツは1981年に販売が禁止され、1990年以降の症例は記録されていません。
有毒成分はR1COOR2(高級脂肪酸R1COOHと高級アルコールR2OHのエステルで、単にワックスともいう)であり、その中毒量は不明とされています。
遊漁対象として人気

バラムツやアブラソコムツは最大で180~200cm程度まで成長する巨大魚でありながら、専門に狙えば比較的簡単に釣れ、スポーツフィッシングの対象魚として人気です。
日本では静岡や和歌山が釣り場として知名度が高く、夜間に水深100~200m程度のポイントを餌を付けたメタルジグでゆっくり誘いながら釣ります。
食味は非常に美味

バラムツもアブラソコムツも、食品としての流通こそ禁止されていますが、個人で釣り上げたものを食べることは可能です。
全身に真っ白な脂を纏った身は、どんな料理にしても激旨。
魚らしい歯ごたえがありながら、甘みある脂がスゥーっと口の中に馴染んでいくお刺身がとくに旨いんですよね……。
僕の知る範囲では、お刺身数切れで下着を汚してしまった友人もいますし、200gくらいのステーキを食べても平気だと言い張る友人もいます。
▼バラムツを特集した記事です
アブラボウズとの関係性

バラムツやアブラソコムツと同じく、全身に脂を纏う魚として挙げられるのがアブラボウズです。
アブラボウズがもつ脂の成分は、ヒトが消化できないエステルとは違い、トリグリセリドであるので適量であれば栄養価も高くて無害とされています。
一方で、脂っこいラーメンを食べた後に下痢をしてしまうような理屈で、過剰に摂取すると下痢を起こすこともあるので食べ過ぎには注意が必要です。
▼脂を持つ理由はコチラの記事で解説しています
イシナギ(肝臓のみ流通禁止)
有毒成分|ビタミンA

出典:PIXTA
ハタの仲間であるイシナギの肝臓には大量のビタミンAが含まれており、イシナギを流通させる場合は肝臓を乗り除く必要があります。
ビタミンA過剰症の症状は、食後30分から12時間以内に激しい頭痛、発熱、吐き気、嘔吐、顔面の浮腫、下痢、腹痛などです。
特徴的な症状として、2日目ごろから始まる顔面や頭部の皮膚の剥離があり、回復には20~30日を要します。
ビタミンAは有毒では無いが……
イシナギの肝臓には10-20万IU/g(1IUは0.3 μgのビタミンAに相当)ものビタミンAが含まれており、5~10g程度の量を食べただけで中毒を起こす可能性も。
ビタミンAが豊富に含まれる食材として知られる鳥レバーが約1g当たり140μgなのに対し、イシナギの肝臓は1g当たり30,000~60,000μgと桁違いです。
中毒の発生状況
イシナギの肝臓が流通禁止になったのは1960年のこと。
厚労省のHPによると、2006年から2015年までに確認されている中毒件数は3件であり、患者数は26人、死者数はゼロです。
オニカマス(流通禁止)
有毒成分|シガテラ

「バラクーダ」という呼び名が浸透しているオニカマスは、シガテラ毒を持つ場合があるので1953年から流通が禁止されています。
シガテラ毒による中毒症状は多岐にわたり、下痢、吐気、嘔吐、腹痛、徐脈、血圧低下、温度感覚異常、関節痛、筋肉痛、掻痒、しびれなどがあり、数か月から1年以上症状が続くことも。
死亡例こそ稀ですが、シガテラ毒を原因とする食中毒は毎年確認されているため、注意が必要です。
シガテラ毒を持つ魚は沢山いる

シガテラは原因となる渦鞭毛藻類が発生する熱帯から亜熱帯地域の食中毒でしたが、近年では本州でも確認されるようになっています。
また、シガテラ毒は特定の魚だけが持つ毒ではない上に、毒の有無を外見では判別できず、調理しても毒が無くなりません。
同種であっても地域差や個体差が大きいこともシガテラの特徴ですので、地域と魚種ごとにシガテラのリスクを把握する必要があります。
オニカマスの他にシガテラのリスクが高いとされる魚種は、バラハタ、バラフエダイ、イシガキダイなどです。
輸入が禁止されている魚も

シガテラ毒を理由に流通が禁止されているのはオニカマスのみですが、輸入が禁止されている魚は他にもいます。
食品衛生法第6条によって規制されている魚種は以下の通りです。
アカマダラハタ 、アマダレドクハタ 、バラハタ、アオノメハタ、オジロバラハタ、マダラハタ、バラフエダイ、フエドクタルミ(ヒメフエダイ)、オニカマス、オオメカマス。
毒魚に注意しましょう

今回は食品として流通が禁止されている魚についてご紹介いたしました。
普通に生活しているだけではまず出会うことの無い魚達ですが、釣り人の皆さんは注意をしてください。
釣った魚を食べる場合は、種類を正しく判別し、毒の有無を確認してから調理するようにしましょう。
撮影:山根央之