ロックフィッシュゲームの必需品である『シンカー』

ロックフィッシュゲームは、根掛かりのリスクが高いポイントをメインに攻める釣りです。テキサスリグや直リグなどさまざまなリグが使われ、リグに合わせシンカーは必需品とも言えます。
ボトム攻略ではシンカーが釣果を左右する事も

ロックフィッシュゲームでは、ボトム攻略が釣果に直結する大切なポイントの一つ。シンカーはそんなボトム攻略において、フォールスピードや根掛かりの回避などにも関わる重要な要素です。
たかがシンカーと安価なものばかり選んでいると、肝心の釣果が伴わずロックフィッシュの楽しさが存分に味わえない可能性もあるのです。
使うシンカーの重さの決め方

シンカーを選びでまず意識したいポイントが、シンカーの『重さ』です。ロックフィッシュで使用されるシンカーは主に3.5から28グラム前後とされていますが、遠投が必要なフィールドなどでは56グラムなどの重いものが使用されることも。
ここまでさまざまな重さが用意されていると、シンカーの重さをどのように決めたらよいか難しく感じますが、選ぶ際のポイントをしっかりと理解すれば誰でも適切なシンカーの重さを決めることができます。
基本は『水深1mあたり1~2g』を目安に

シンカーの重さを決める際はまずキャストするポイントの水深を意識しましょう。ロックフィッシュではリグを海底まで着底させ、ボトムを感じながら釣りをすることが基本となります。そのため水深1メートルに対して1~グラムの重さを目安に考えるとよいでしょう。
例えば、水深が5メートルの場合は5~10グラムの間、10メートルなら10~20グラムといった具合に、凡そのシンカー重量を決める事が出来ます。
水深やボトム形状が読めない場合は『軽め』から
はじめて訪れるフィールドで水深やボトムの変化が読めない時には、軽めの重さがおすすめ。重いシンカーはボトムをしっかりと感じられるメリットがあるものの、ストラクチャーや根がきついポイントでは根掛かりのリスクが高く、一投目でいきなりルアーロストという悲劇に見舞われます。
前出の『水深あたりのシンカー重量』の範囲で最も軽い重量を最初に選び、カウントダウンをしながら水深をしっかりと把握。ボトムの形状等確かめながら徐々に重たいものを使っていくと手返しよく釣りを楽しむことができます。
遠投が必要だったり潮流が速い場合は徐々に『重く』
沖を攻める必要がある場合はシンカー重量を重くすることで飛距離を伸ばす事ができます。また、防波堤の突端や磯場などの潮通しのよいポイントでは、リグが流されてしっかりとボトムを取れない状況になる事があります。
このようなシチュエーションではシンカーを重くして対応しましょう。もちろん急激に重くするのではなく、徐々に重くすることで根掛かりのリスクを軽減できます。
シンカーをローテーションしてベストな重さを探るのが重要

ロックフィッシュにおけるベストなシンカーの重さは、ずばり『ボトムをギリギリ感じられる』グラム数です。ポイントの状況やタックルセッティングでボトム感度はガラっと変わるため、ベストなシンカー重量は人によって異なります。
最も避けるべきは、根掛かりするorボトムが取れないにも関わらず、面倒が故同じシンカーやリグを使い続ける事。自分なりの『ボトムをギリギリ感じられる』感覚は、同じポイントでシンカーやリグのローテーションをする事で養われていくのです。
各シンカー素材の特徴と、メリット/デメリット

ロックフィッシュで使用されるシンカーは、素材によってさまざまなメリットやデメリットがあります。価格によるコストパフォーマンスはもちろん、素材によって感度や飛距離などにも大きく影響を与えるため、それぞれの素材の特徴はシンカーを用意する前に必ずチェックしておきましょう。
鉛シンカー

シンカーの素材の中では最も価格が安い鉛シンカー。根掛かりによるロストが多くなるロックフィッシュの釣りにおいては、コストパフォーマンスに優れた素材です。
しかし、素材が柔らかいため感度が悪く、スタックした際にもシンカー自体が変形し、めり込むように根掛かりしてしまうというデメリットもあります。
ブラスシンカー

ブラスシンカーは、鉛素材のものに比べると若干価格は高めではあるものの、鉛よりも硬度が高いゆえボトム感度に優れ根掛かり回避性能の高い素材です。
ただし比重は全シンカー素材中一番小さく、同重量ではブラスの表面積が最も大きくなるため、遠投などの飛距離が必要なシチュエーションには不向きというデメリットも。しかしながらこの表面積の大きさのお陰でスローフォールが可能で、喰いの渋い状況ではその強さを発揮することもあります。
タングステンシンカー

タングステンシンカーは、現在シンカーとして用いられる素材の中で比重と硬度がもっとも高く、感度、根掛かりの回避性能は非常に優秀な素材です。表面積も小さくなるため、遠投が必要なシーンや逆風下でも他のシンカー素材の追従を許さないキャスタビリティを発揮します。
性能だけ見れば最強のシンカー素材ですが、唯一のネックは『価格』。タングステン自体が希少金属であるため30グラム前後のものが1個1,000円弱するなど、シンカーとしてはとても贅沢なお値段なのです。
硬質鉛シンカー
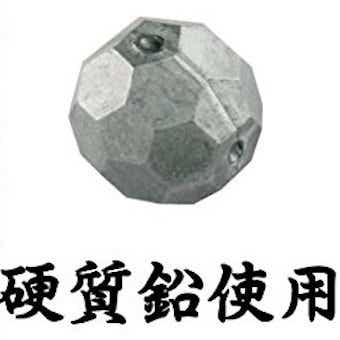
通常の鉛シンカーに比べて硬い硬質鉛を使用しているのが硬質鉛シンカー。鉛にスズ等の金属を混合することで硬度が高められ、ボトム感度に優れたマテリアルへと改良されています。比重は鉛そのものなので表面積も小さく遠投性にも優れています。
材料が比較的安価で製造コストもかからないためコストパフォーマンスも高いのですが、現在のところ既製品が少なく形状やウエイトが限られるのがデメリット。今後の進化を期待したい素材です。
結局どの素材がいいの?
シンカーはそれぞれの素材によってメリットとデメリットがあるため、素材の特徴やフィールド、コストパフォーマンスなどのさまざまな側面から自分にマッチした素材を選ぶことが大切。
狙う魚種、ボトム形状や魚の活性などその時の状況に合わせてシンカー素材を使い分けるのがベストと言えるでしょう。
シンカー形状別の特徴とメリット・デメリット

ロックフィッシュに使用するシンカーは専用モデルだけでもさまざな形状のものが販売されています。近年はゲーム性の高さを求めてバスフィッシングやライトゲームなど、他の釣りのシンカーを流用するアングラーも増えてきており、シンカーの形状一つでアプローチの仕方が大きく変わるのもロックフィッシュの魅力。
それぞれの形状の特徴やメリット、デメリットをしっかりと理解すると釣果にも大きく影響してきます。
バレットシンカー

ロックフィッシュゲームはもちろん、バスフィッシングなどでももっとも人気の定番シンカー。テキサスリグにもっとも相性のよい形状とされており、根掛かりの回避率が高く、根の下までしっかりとリグを落とし込め、水面方向への抜けも良いというメリットがあります。
バレットシンカーは鉛はもちろん、タングステンやブラスでも製造されている形状で好みの素材を選べるのもポイントです。
スティック型シンカー

テキサスリグに次ぐ次世代のリグとしてロックフィッシュでも注目されるフリーリグや直リグで用いらる形状。これらは通常のバレットシンカーではリグを組むことができないため、スティック型の専用シンカーが必要です。
バレットシンカーに比べるとボトム方向への貫通力が高く、フォールスピードも早いためロックフィッシュ向きの形状ですが、水面方向への抜けが悪いというデメリットも。海藻ジャングルから魚を引き抜くような釣りにはあまり向かないと言えます。
ドロップ型シンカー

ボトムでの根掛かりの回避性能がもっとも高いドロップ型シンカー。昆布帯などにリグを落とし込むシチュエーションには不向きであるものの、ゴロタ場などでのスタックの回避率がもっとも高い形状です。ロックフィッシュトーナメントなどで人気を集めているビフテキシンカーもこの形状です。
キャロシンカー(中通し)

ワームをよりフリーにさせ、ナチュラルにアピールしたい状況にはバスフィッシング用のキャロシンカーもおすすめ。シンカーストッパーとスイベルを組み合わせることでキャロライナリグを組むことができるため、ロックフィッシュに流用するアングラーも増えてきています。
おすすめのロックフィッシュ向けシンカー
最後に各メーカーから販売されているロックフィッシュ向けのシンカーを紹介します。ロックフィッシュ専用設計のシンカーはもちろん、バスフィッシング用として販売されているものの中にもロックフィッシュにぴったりのシンカーは多数あります。
素材や形状を見ながら幅広いメーカーを探してみましょう。お気に入りのシンカーが見つかったら使い分けができるよう、重量別に揃えるのもおすすめです。
ダイワ HRF TGシンカー
デコイ テキダンシンカー
ジャングルジム TGビーンズ
フィッシュアロー フリリグシンカーTG
プロズワン クランクシンカー
レイン ベーシックバレット
お気に入りのシンカーでロックフィッシュを楽しもう!

ロックフィッシュはさまざまなリグを使った釣りが基本となるためシンカーは必需品とも言える大切なアイテム。ウエイトはもちろん、素材や形状なども意識してシンカーを選ぶことで釣果アップにつながることはもちろん、ロックフィッシュの奥深さを更に感じる事ができますよ!









