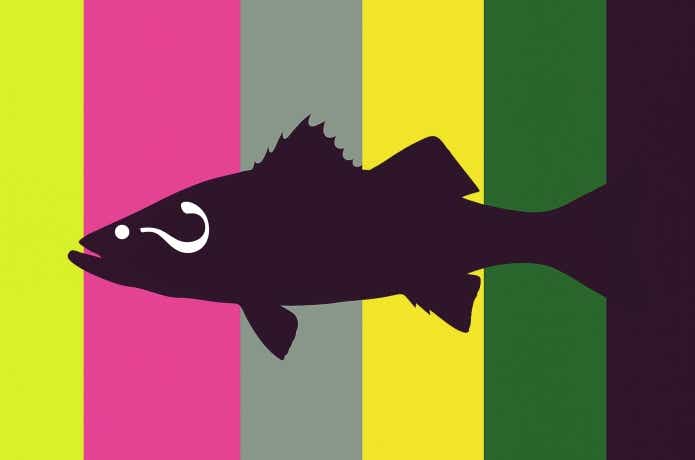「今は何色が釣れていますか?」

毎日お客様を乗せてガイドしていると、実にさまざまなご質問をいただきます。
中でもとくに多いのが、「釣れるカラー」についてのご相談です。朝一番、「今は何色が釣れていますか?」と聞かれるのは、もはや日常茶飯事。

須江
今回は、そんなシーバス釣りにおけるカラーの話をじっくり掘り下げていきます。
カラーよりも重要なことがある

結論から言うと、カラーは釣果を左右する最重要な要素ではありません。魚を釣るために大切な要素の中でも、優先順位はかなり低いんです。
具体的には、「釣れるポイント → 釣れるタイミング → 釣れるレンジ → ルアーのシルエットとアクション」、そして最後に「カラー」という順番になります。

ですが、いわゆる“アタリカラー”は確かに存在していて、そのことからも魚はカラーをしっかり認識していると感じます。

須江
ただし、重要なのは順番。まず意識すべきはルアーのシルエットやアクションで、それが合っていないと、魚はそもそもルアーに反応してくれません。
アタリ(ハズレ)カラーの存在と確立

釣り人なら誰しも気になる「アタリカラー」の存在。これは、その日・その時間帯にもっとも釣れるカラーを指す言葉です。
僕の経験上、アタリカラーは確実に存在していて、これを使うとバイトの数が増えたり、深くしっかりと食ってくるようになったりと、結果的にバラしにくくなります。つまり、自然と釣果も伸びやすくなるというわけです。
ただし、その逆である「ハズレカラー」もあるのが事実。こちらはバイトが減ったり、浅い食い方で掛かってもすぐにバレてしまったりと、残念な結果を招くこともあります。

制作:TSURI HACK編集部
多くの人が「アタリカラーを当てたい!」と思っていると思いますが、僕の感覚では、10色のうち1色がアタリカラー、1色がハズレカラー、そして残りの8色は普通に釣れる“中間色”です。

須江
つまり、9色は釣れる色で、釣れないのは1色だけ。この“ハズレ”さえ引かなければ、普通に釣れるんです。
ハズレカラーを避けるために
カラーは大きく分けて、以下の4つの系統があります。
| 系統名 | 代表的なカラー例 |
|---|---|
| ペイント系 | チャート、レッドヘッド |
| フラッシング系 | シルバー、ゴールドベース |
| ゴースト系 | 半透明カラー |
| 特殊系 | グロー、ケイムラ |
ルアーを選ぶときは、これら異なる系統から最低2タイプ以上を揃えておくのがおすすめ。
そうすることで、ハズレカラーを引く確率をグッと減らせます。
「その定説、本当?」色選びに“例外”はつきもの
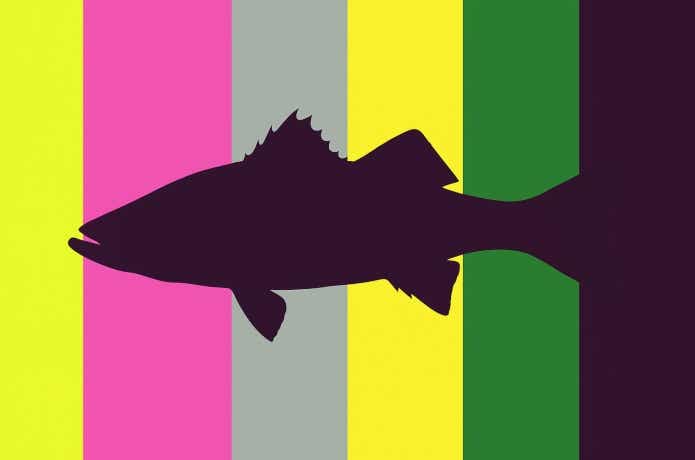
制作:TSURI HACK編集部
「濁ったらチャートやゴールド」「ベイトがコノシロならコノシロカラー」といった、いわゆる“釣れるカラーの定説”がありますよね。
でも正直なところ、僕はそれがすべて正しいとは思っていません。実際、カラーの効き方にはもっと複雑な要素が絡んでいると感じています。

たとえば季節によって、効くカラーには明確な違いがあります。
真冬は赤が強く、逆にチャートはあまり反応が良くないことが多い。
なぜかと聞かれても、魚じゃないので正直分かりませんが、経験上そういう傾向は確かにあるんです。

場所によっても違いが出ます。
「このポイントではこのカラーが強い」と感じる場面は多く、ベイトの種類が通年で変わらなかったり、潮の色や水質の特徴が影響しているのかもしれません。

時間帯による変化もあります。
以前、同じ場所で朝はチャートにしか反応しなかったのに、夕方になると赤やオレンジでしか口を使わない、なんてこともありました。

さらに、ある日は「今日はチャートが当たりカラーだ」と感じた場面で、ルアーのどこか一部……たとえば腹や頭、尻尾などにほんの少しチャートが入っているだけで釣れる、ということも。
そうなると、全体がその色じゃなくても、どこかに入っていればいいという場合もあるんです。

須江
そんなふうに、定説にとらわれすぎず、状況や経験を踏まえて柔軟にカラーを選ぶことが、釣果につながる大事なポイントだと僕は思っています。
本当に釣れる色は“魚が決める”

「イワシベイトのときはイワシカラー」「コノシロベイトのときはコノシロカラーが効く」などとも言われますが、本当にそうでしょうか? 僕はそう単純な話ではないと思っています。
実際、ベイトフィッシュの色にルアーを寄せたからといって、それが魚にとって本当に“マッチ・ザ・ベイト”になっているとは限らないんです。

たとえば、東京湾で見かけるイワシはカタクチイワシが多いのに、市販のイワシカラーの多くはマイワシを模したもの。
そもそも見た目からして違っていることも珍しくありません。つまり、ベイトと同じ色だから釣れるとは限らないということです。

それでも、「強いカラー」は確実に存在すると僕は感じています。
たとえば、カタクチイワシがベイトになっている日中の釣りでは、意外にもパールホワイトにオレンジベリーやレッドベリーといったカラーがよく効くんです。
本来はナイトゲームでよく使うようなカラーですが、魚がどのように見ているのかは分からなくても、実際に釣果が出ている以上、それが“正解のカラー”ということなんだと思います。

須江
見た目を完全に再現するよりも、魚にとっての“刺激”や“認識のしやすさ”のほうが大事なのかもしれませんね。
釣り人にとっての“釣れるカラー”論

魚から見て「釣れるカラー」があるのと同じように、釣り人にとっても“釣りやすいカラー”というのは確実に存在します。
基本的には、目立つカラーのほうが釣果につながりやすい場面が多いです。
たとえば、コノシロパターンのビッグベイトでは、ルアーのアクションがちゃんと出ているかを目で確認できることが釣果アップの鍵になります。

須江
動きが見えやすいカラーを選べば、自信を持って使い続けられますし、調整もしやすくなります。

また、ストラクチャー周りを狙う釣りでは、キャストの精度が大事。
見やすいカラーならルアーの弾道が把握しやすく、外したと思えばすぐに止める判断もできるので、自然と精度も上がっていきます。

さらにナイトゲームでも、視認性の高いカラーを使うことで、ルアーを正確に明暗の境など狙ったポイントへ届けやすくなり、結果として釣果も伸びていきます。

須江
見やすいカラーは魚に対してだけでなく、釣り人自身の精度や判断力をサポートしてくれるという点でも“釣れるカラー”なんです。
カラーにまつわる面白トピック

「あのカラーが釣れる」といった話以外にも、カラーにまつわる面白い考え方はたくさんあります。
たとえば、同じスポットで釣りを続ける場面では、カラーローテーションが非常に効果的です。
とくにストラクチャー周りやジギングなどでは、同じ色を使い続けていると魚がスレて反応しなくなることもあります。

須江
そんなときは、思い切ってカラーを変えてみると、またすぐに反応が出ることも珍しくありません。

また、チャートのような派手な色は確かにスレやすい傾向がありますが、それと同時に「目立つ=見つけてもらいやすい」というメリットもあるので、魚がいる場所を探すときには強い味方になります。
ただし、狭いポイントでは目立ちすぎると逆効果になることもあるので、使いどころには注意が必要ですね。
さらに、ルアーの種類によっても、カラーの影響度は変わります。
とくに視認性の高いビッグベイトなどは、色の違いが釣果に直結しやすく、動きで見せるルアーほどその傾向が強くなります。

そしてもうひとつ、メタルジグもカラーの差が出やすいルアーの代表格です。
とくにフォール中にバイトが出やすいシーバスジギングでは、アクションではなくジグそのものが仕事をする場面がほとんど。
形状やウエイトに加えて、カラーもいくつかバリエーションを持っておくことで、状況に合わせた選択ができるようになります。
何が釣れるか、答えは海の中。

僕なりのカラー論を語ってきましたが、正直、どのカラーが釣れるかなんて魚じゃない僕には分かりません。答えになっていないかもしれませんが、それが本音です。
とはいえ、「釣れるカラー」が確かに存在するのも事実。
だからこそ、先入観にとらわれず、いろんなカラーを試してみてほしい。そうすれば、少しずつ自分なりの“答え”が見えてくるはずです。

須江
そして何より、カラーはあくまで“最後のピース”。焦らず、楽しみながら見つけていきましょう。
撮影:須江一樹