クロサギについて

今回の主役となるのがクロサギという魚。
本命として狙う人がいないばかりか、外道としても影の薄い存在です。
この写真を見て「あれってクロサギだったのか」って思った人もいるのではないでしょうか。
そんな不人気かつ無名な魚にスポットライトを当てることにしました。
分類
クロサギはクロサギ科クロサギ属の海産魚で、科から種名までが同じなのでクロサギ属を代表する魚だと言えます。
学名はGerres equulus。種小名のequulusはラテン語で馬を意味するそうで、新種として発表された当時の人の感性では、どこかに馬の面影を見出したのかもしれませんね。
形態と生態
痩せたクロダイのような雰囲気で、体高が高くて平べったい姿をしており、前方が長い特徴的な形の背鰭を持っています。
体長は最大で25cm程になり、25cmになるまでには8年ほどかかると考えられており、成長が遅い魚と言えるでしょう。
おもに海底に棲むゴカイや甲殻類を餌としていて、産卵は夏に行われます。
分布及び生息域
クロサギは本州・四国・九州の沿岸域、とくに内湾や汽水域を好んで生息します。
同じ地域には近縁種のダイミョウサギも生息しているのですが、姿形が非常に似ているので見分けが困難です。
ダイミョウサギは最大15cm程なので、20cm以上だとクロサギと同定して間違いないと思いますが、それ以下のサイズなら背鰭の棘の数(クロサギ9棘、ダイミョウサギ10棘)を見るしかありません。
ちなみに、奄美大島近海以南にはミナミクロサギが生息しますが、こちらは採捕地で見分けられます。
流通状況と市場価値
市場価値は「ほとんど無い」と言えます。
市場に流通することはほとんどなく、世間の認知度はかなり低いはずです。
加えて「身が臭い」という評判も不人気の理由でしょう。噂によると、麦飯や干した布団の臭いがするそうです。
おもしろい特徴が2個ある
口が飛び出る

クロサギは海底に潜む甲殻類や環形動物を餌とするため、口が下に向かってかなり大きく飛び出ます。
マトウダイやマアジは水と一緒に餌を吸い込むので前方に飛び出しますが、クロサギは餌を泥ごと吸い取るために下を向いています。
餌を濾しとった後に泥だけを鰓から排出するようで、ちなみにヒイラギも同じ形の口です。
めっちゃ腹黒

お腹を開けると黒く、これは腹腔膜が黒い色をしているからで、この黒さが名前の由来にもなっています。
しかし、なぜ黒いかはわかっていません。
同じ腹黒な魚としてサヨリが挙げられますが、サヨリは海面直下を泳ぐため、強い紫外線から内臓を守るために腹腔膜が黒いです。
しかし、クロサギはどちらかというと海底付近を泳ぐ魚なので、紫外線対策というのは考えられず、謎は深まるばかり……。
クロサギを釣ってみた
夜の河口

穏やかな内湾の砂浜ならどこにでもいるらしいのですが、今回は餌が豊富そうな河口をチョイスしました。
じつは一度日中に狙ってみてボウズだったので、大学終わりの夜釣りで再挑戦。
釣り方はチョイ投げ
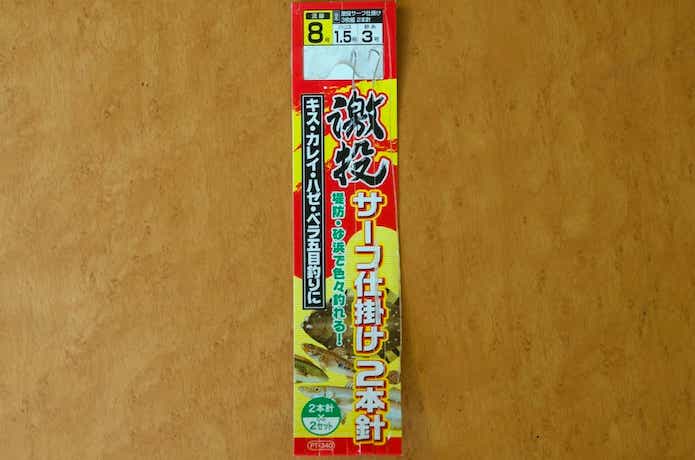
砂や泥底の餌を食べる魚なので、釣り方はチョイ投げにしてみました。
25cm程度になる魚ですが、小さな口で吸い込んで捕食するため、針は小さめの流線が良さそうです。
手元にあった最小サイズが8号だったのでこれを使いましたが、本当はもうちょっと小さめが良いかもしれません。
いきなりシロギスが登場

仕掛けを投入してすぐにシロギスがヒット!
普通は大喜びですが、今日に限っては外道。大本命は、干した布団臭いアイツです。
幸先の良いスタートだったものの、このシロギスが釣れてからアタリは一切なくなってしまいました。
大きなアタリ

あれからどれぐらいの時間が経ったのかわかりませんが、ウトウトしていると突然鈴が鳴って飛び起きました。
竿尻が浮き上がるほどの大きなアタリです。
慌てて竿を手に取ると、アタリの大きさの割には引かないというか、ほぼ無抵抗な状態で上がってきました。
“本命の外道”が登場

ついに本命の外道、クロサギが登場!
20cm程だったので、ランカーサイズと言っても過言ではないでしょう(笑)
光を当てて写真を撮ると白飛びしてしまうほど銀ピカ。鮮やかな黄色の鰭も合わさってとても派手です。
やっぱり、どんな魚も図鑑で見るよりも実物の方が美しいですね。
クロサギを食べてみた

クロサギは鮮度が落ちやすい魚です。持ち帰る場合は、釣り場で血抜きをして内臓も取ってしまいましょう。
捌き方は他の魚と大差ありませんが、身が柔らかいので注意してください。
懸念していた臭いですが、腹腔の中に鼻を近づけて嗅いでも他の魚と同じくらいで、調理している段階では気になりませんでした。
刺身

身が柔らかくて崩れてしまいそうだったので、皮を引かずに刺身にしてみました。
筋肉にも黒い色素が含まれているようで、くすんだ色をしていてあまり見た目が良くありません。
予想通り食感はかなり水っぽいものの旨みは強く、なかなか美味しいと思います!
昆布締めで水気を飛ばすとさらに美味しく食べられそうに感じました。
塩焼き

火を通すと印象はガラリと変わって、ホクホクしていて身切れがよく、上品な味わいに。
水分が飛んだ分、旨みも凝縮されたように感じます。
味とは直接関係ありませんが、水分が多いので焼くと身がかなり縮んでしまいます。
ムニエル

ムニエルにもしてみました。
クロサギは脂が少ないのですが、バターのコクが加わって濃厚な味わいに。
結局、臭いの?
今回クロサギを食べてみて、どの調理方法でも臭さを感じませんでした。
少し考えたのですが、生食はともかく、塩焼きやムニエルは強い火力で火を通すので、水分や油と共に匂いの元となる成分が揮発したのかもしれません。
今回は試せませんでしたが、蒸したり茹でたりすると印象は少し変わるのではないでしょうか。
とくに蒸し料理はゆっくりと火が通り、魚から水分がなくなりにくい調理方法であるため、理屈的には臭いが際立ちやすくなります。
白身魚は蒸し料理に用いられやすいことを踏まえると、「クロサギを蒸して食べたら臭かった」というのが悪評の元かもしれませんね。
外道を狙うのも楽しい!

いつもは気にも留めないのに、いざ狙ってみるとなかなか釣れないのが外道というもの。
外道といえども、試行錯誤して釣れた時の嬉しさは一入です!
外道も狙って釣れるようになってこそ、釣り名人と言えるのかもしれませんね。
撮影:あらた






