サワガニとは

サワガニはエビ目・カニ下目・サワガニ科に分類される日本固有種のカニで、本州から四国、九州の屋久島までの淡水域で一生を過ごします。水がきれいな渓流や小川の上流から中流域に多く、春から秋に活動し、冬には川のそばの岩陰などで冬眠します。

甲幅は20ミリを超し、足を含めると50~70ミリほどで、丸みのある滑らかな黒褐色の甲に朱色の足のものが多いですが、地域によっては紫や青みがかった体色のものも見られます。
サワガニを捕まえよう

サワガニは水がきれいな河川の上流から中流域に多く生息しています。そのなかでもサワガニガ好む川底が石や砂礫で隠れられるような岩がある場所を探しましょう。支流の分岐や落ち葉が引っかかるような場所も好みです。

一番簡単な方法は川の中の石や岩をひっくり返して、潜んでいるサワガニを見つけることです。サワガニがいたら甲羅を左右からそっとつまみ上げ、動かした石や岩は元の位置にそっと戻しましょう。

サワガニを見つけても逃げられてなかなか捕まえられないときは、割り箸や枝などにサキイカをくくりつけて、岩の間や石の下にそっとたらすとサワガニが食いついてきて捕まえることもできます。
夏休み 自由研究 お魚観察ケース セット
伸縮する棒1本と昆虫網と魚網が1つづつセットになっています。棒は兼用できてコンパクトになるのでリュックなどに入れて持ち歩くことができます。
エーワン コンパクト水陸両用網
サワガニ獲りの時期は?
サワガニの旬は春から秋ですが、冬眠中のものが美味しいとも言われています。春から秋は活動期で見つけやすく、冬眠中は岩陰や沢の土砂の中に潜ってしまうので見つけにくくなりますが、サワガニの繁殖場所を知っていたりサワガニが隠れるポイントが分かってくれば見つけることができます。
サワガニの飼育

サワガニは甲羅が滑らかで美しく観賞用としても人気があります。飼育するには陸の部分も広く作る必要があるため大きめの水槽がおすすめです。足を使って脱走するのでフタ付のものにしましょう。水槽の底に砂利を敷き、水の深さは3~5センチほどでサワガニが隠れられるような瓦や石と登れるような木や石も入れましょう。
注意点
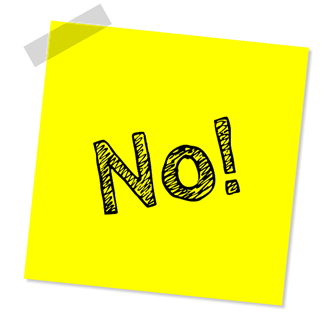
サワガニの甲羅は脱皮直後とてもやわらかくなっています。このときは共食いされやすいので複数飼育するときは気をつけましょう。甲羅を手で触るのも良くありません。
温度管理
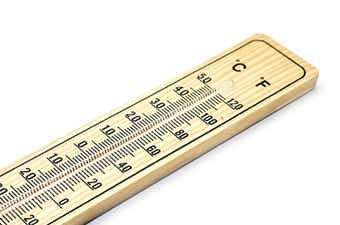
サワガニは水温が30度を超すようなところでは生きられません。水槽内の水量が少ないため外部の温度に影響されやすいので夏場は水温管理に気をつけましょう。
冬眠に備えて
サワガニは冬に冬眠します。気温が下がってくる11月中旬頃からエサの量が減ってくるのでそれに併せて徐々にエサを減らします。土や瓦のかけらを入れておくとその中に潜って冬眠するので凍らないような場所に置いておきましょう。
餌
サワガニは雑食で昆虫、ミミズ、藻類など色々なものを食べます。市販されているカニ用の餌のほか、ご飯粒や鰹節、キャベツ、シラスなども餌になります。
イトスイ ザリガニ・カニの主食 40g
飼育用の水槽
水槽と上部フィルターがセットになっているフタ付の水槽でサワガニの飼育も安心です。ろ過材やカルキ抜きもセットになっているのですぐに飼育を始められます。
GEX ジェックス マリーナ600 水槽&フィルターセット
サワガニのレシピ

サワガニはとても美味しく、養殖もされているほどです。小さくて裁くのが難しいためほとんどは丸ごと調理して食べます。から揚げではカニの風味と香ばしさ、旨みを味わえます。とくに小さなものは佃煮として食用されています。
加熱はしっかりと!
サワガニはジトマスという寄生虫の宿主となっていることが多いので、食べる際は必ず70度以上の高温でしっかり火を通してから食べましょう。調理した手は他のものを触る前にきちんと洗いましょう。
レシピ例
サワガニの唐揚げ(楽天レシピ)
沢蟹の甘辛おかず(楽天レシピ)
サワガニは身近にいます!

河川の上流から中流域で多く見られるサワガニですが、水がきれいであれば都市部の小川でもサワガニを見つけることができます。まずは身近な川の石をそっと持ち上げてみましょう。慣れてくるといそうな場所が分かってくるのでたくさん捕まえることもできますよ!
Let’s search for Sawagani!
サワガニを探そう!






