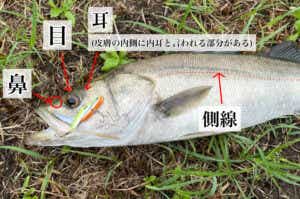釣れなくなる原因『夜光虫』

メバリングやシーバスなんかのナイトゲームをしているとよく発生している夜光虫。
見ているととても綺麗で癒やされますが、釣りには悪影響を及ぼすことが知られています。
夜光虫の何がいけないのか
夜光虫発生時のデメリット
-
1.ルアーやラインが光る(魚が警戒する)
-
2.酸素が少ない(活性が下がる)
-
3.魚自体も光る=(魚が浮きづらくなる)
デメリットが多く夜光虫。発生したら、釣り自体しない人も多いのではないでしょうか。
しかしながら、狙い方によっては釣果を出すことは可能なのです。
今回は、そんな夜光虫発生時の釣り方をご紹介したいと思います。
夜光虫発生時の攻略法
大量発生時は諦めよう

夜光虫が大量に発生し、水面を刺激しなくても青白く光っているようなとき。
このような状況下では、釣りをしないのがベターです。
夜光虫により、酸素量が圧倒的に少なくなり、ほとんどの魚は居ないか口を使いません。
明らかに水面が青々としていたら、即移動です!
釣りはゆっくり!基本は光らせないことを意識する
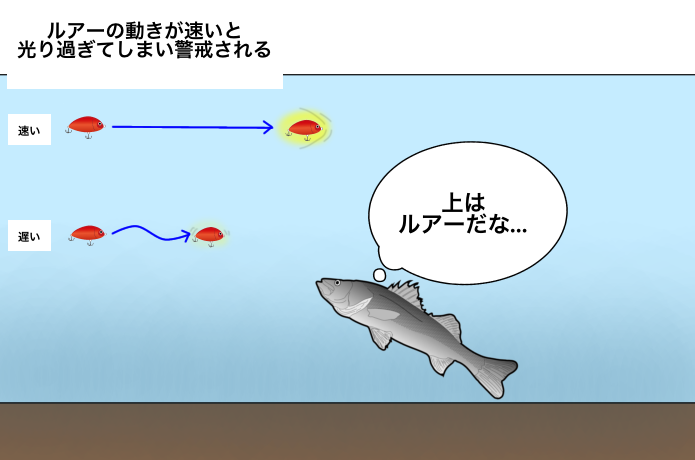
ルアーやラインが光らないように気を付けるのが基本です。
夜光虫は刺激を加えると光るため、アクションを控えたり、巻くスピードを緩めたりすると、光づらくなりますよ。
プラグメインで釣る

プラグを中心に使うのも、釣果を伸ばすコツです。
ワームは動きを止められず、常に夜光虫が光ってしまいます。
ラインも常に水中を切るような動きになってしまうので、ゆっくり巻けるプラグを使用しましょう。
レンジを入れる
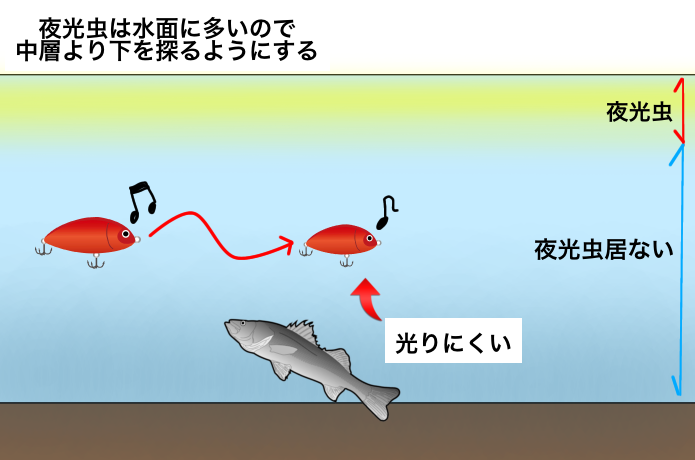
夜光虫は表層に発生すると言われています。
水面をラインが叩いたり、表層系ルアーで狙ってしまうと光らせてしまい余計なプレッシャーを与えてしまいます。
そのため、夜光虫が居ないレンジにルアーとラインを持っていくことが大切です。
流れの向きを意識
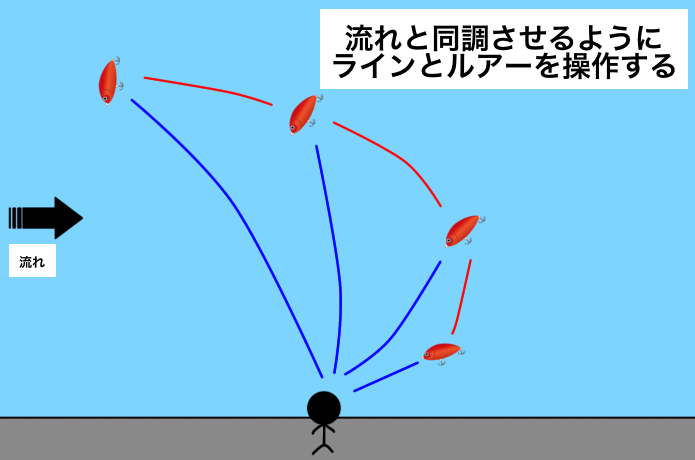
おもにラインが光らないようにするために、流れの向きを理解します。
上流に向かって投げ、ラインと流れを同調。もしくは、流れに準ずるように引いてくることがコツです。
さらに釣果を伸ばすポイント

夜光虫が発生したとき、さらに釣果をあげるためのポイントがあります。
細かなセッティングや攻め方を変えるだけで、釣果が全然変わってきますよ。
リーダーを細くする

経験上、ルアーが光ることよりも、ラインが光ることに気を配ったほうが釣れます。
そのため、極力リーダーを細くしましょう。リーダーが太すぎると、プランクトンに当たって光ってしまう面積も増えてしまいます。
いつも使っているリーダーよりも、一段階細いものを選ぶように心がけましょう。
リーダーを長めにする
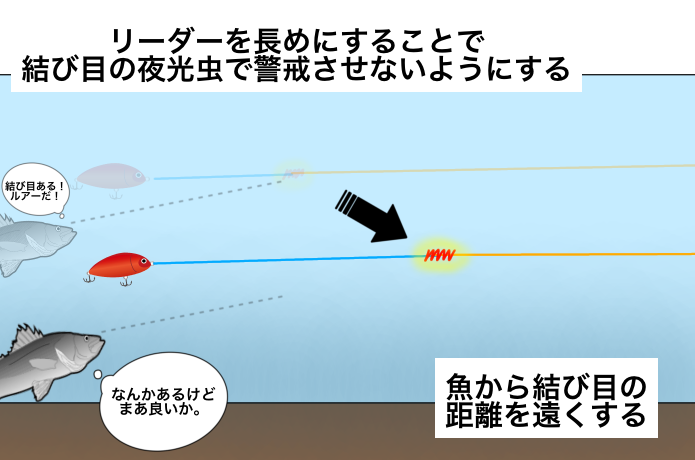
PEやエステルを使用するとき、必ずリーダーを結びますよね。
その結び目が光やすいのです。ルアーから近い位置で光ってしまうと、魚を警戒させてしまう可能性があります。
そのため、リーダーは長くしましょう。ルアーから結び目までの距離を長くすることで、極力プレッシャーを与えないようにしましょう。
動かないルアー

動かないルアーを扱うことも必要です。
リップ付きのルアーは、水の抵抗も強く動きますよね。そのため、夜光虫で光りやすくなります。
こういうシチュエーションでは、動かないルアーが活躍するので、ぜひ一本はボックスに入れておくようにしましょう。
サスペンドルアーを使用して、ルアーを止めることも有効なので、試してみてください。
ボトム攻略
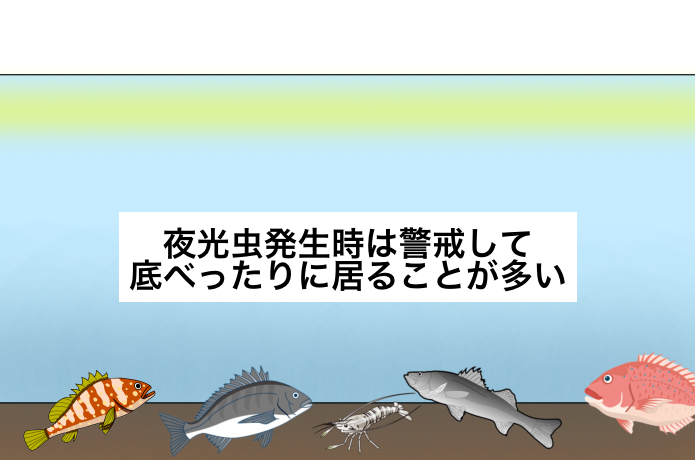
夜光虫が発生しているとき、必須になるのがボトム攻略です。
表層付近は夜光虫が増え、酸素も少なくなります。
そのため、ボトム付近が光にくく、魚が溜まっているエリアとなるのです。
見切りも大切だけど…
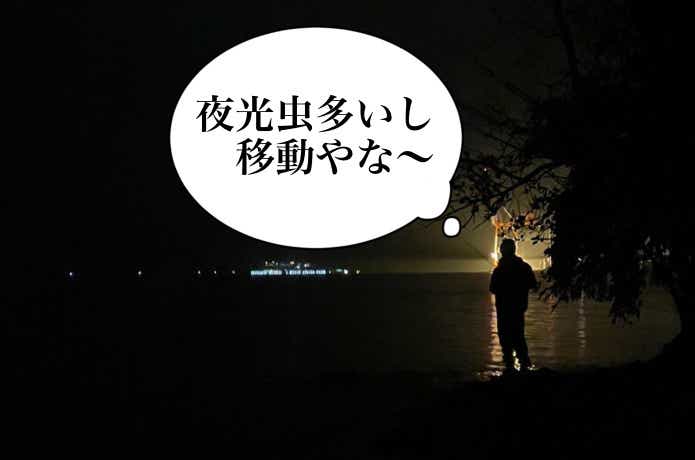
釣り場を早々に見切ることも大切です。
あまりに釣れない状況や夜光虫が多すぎる状況では、キッパリと諦めてしまいましょう。
より夜光虫が少なく、魚がいる場所を選ぶことが重要です。
釣れないと思っても諦めない!

やはり夜光虫発生時は、厳しい状況が多いです。
しかしながら、夜光虫発生時の釣り方は、他のシチュエーションでも使えるスキルが多いです。
スキルアップのためにも、ぜひ今回の記事を参考に、夜光虫が出ていても諦めずに頑張ってみてください。