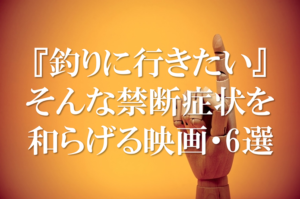アングラーとは

アングラー(angler)とは
英語で「釣り人」を指す名称です。同様にフィッシャーマン(fisherman)も釣り人を指しますが、フィッシャーマンは漁師など、職業的に魚を獲る人たちを指すニュアンスが強く、趣味性で魚を獲る人の事をアングラーと呼ぶ事が一般的です。
「釣り」自体を指す英語も、アングリング(angling)というものがあり、 アングリングは趣味の為に魚を獲る事、フィッシング(fishing)は趣味・商売の為に魚を獲る事とされています。
アングラーにまつわる作品達

釣りは多くの時間や労力、それにお金も必要になってくる趣味です。高い船代を出してボウズを食らい、それでもまた釣りに行くお父さん。そんな姿をみて不思議に思った方も多いのではないでしょうか?
人はなぜ釣りに行き、アングラーになるのか。ここでは釣り人や魚釣りの魅力について触れられる作品達をご紹介します。
ヘミングウェイ釣り文学傑作集
20世紀の文学界に多大な影響を与えたヘミングウェイ。その名だたる作品の中から、釣りに関わるシーンを選抜した作品です。ノーベル文学賞を受賞した彼の言葉は、「釣り」という存在がなければ生まれなかったかもしれません。
ヘミングウェイ釣り文学傑作集
釣人かく語りき
釣りとは何か?人はなぜ釣りをするのか?各界の著名人へのインタビュー集。
つり人社 釣人かく語りき
文豪たちの釣旅
大岡 玲著「文豪たちの釣旅」文豪達が愛した「釣り」を巡る旅を記した一冊。
文豪たちの釣旅 (フライの雑誌社新書)
ブラックバス
直木賞作家・神吉拓郎著の短編集。「ブラックバス」はその中一編で、終戦の日に疎開先の湖でブラックバスを釣る少年の心情が静かに描かれています。本作は直木賞最終候補作にまで挙がった隠れた名作。
ブラックバス(文春文庫)
リバー・ランズ・スルー・イット
ロバート・レッドフォードが15年の歳月をかけ作り上げた玉砕のヒューマンドラマ。フライ・フィッシングの美しい描写は、第65回アカデミー賞・撮影賞を受賞しました。モンタナの雄大な自然の中で、若き日のブラットピットの名演が光ります。
リバー・ランズ・スルー・イット [Blu-ray]
ビッグ・フィッシュ
巨匠ティムバートンが手がける、父と子の絆の再生をテーマにしたハートフルファンタジー。釣りのシーンはあまり出てきませんが、人生の傍にはいつも魚釣りがあると感じさせてくれます。
ビッグ・フィッシュ コレクターズ・エディション [DVD]
アングラーになろう!

ただ魚が食べたければ魚屋に行くほうが圧倒的に安上がりです。それはどんなに沢山の魚を釣リ上げる名人でも同じ事です。人はなぜ釣りに行くのか?その答えはアングラー(釣り人)にしか分からないものなのかも知れません。