やっぱり魚は減っていた

編集部I
村岡さん、東京湾のシーバスが釣れなくて困っています。
昔はたくさん釣れたと聞くこともあるので、魚が減ってるんじゃないの!?って思っているんですが、どうでしょう?
村岡さん
はい。確かに釣れなくなってきているのは、間違いありません。
編集部I
やっぱり!
村岡さん
ただ、同様に釣り方と釣具が進化しているので、釣果自体は落ちていませんよ。
編集部N
I君の腕の問題だね?
編集部I
そうですね……。
村岡さん
しかし、ハイシーズンに入ってくる魚の量が減っていますから、釣れない人も多いでしょう。
編集部I
ほらね~!聞きました?Nさん!だから言ったじゃないですか~!(ドヤ)
編集部N
なんだコイツ腹立つな
編集部I
昔と比べて、どの程度釣れなくなっているのでしょうか?
村岡さん
自分の体感ですが、10年前と比べてシーバス=スズキの量は半分ぐらい。
編集部I
半数!?そんなにですか……

村岡さん
そうですね。特にガイド船なんかは、昔は3桁は当たり前。100、200と数を出していました。
ところが、今は走り回らないと釣れない。悪ければ1ケタ台の釣果で終わることもありますよ。
編集部I
沖にはたくさんいるイメージでしたが、違うんですか?
村岡さん
遊漁船の船長たちも口を揃えて言っていますが、東京湾に生息するスズキが減っています。
なぜ、魚が減っているのか?
編集部I
東京湾のスズキが減っている……なぜですか?
村岡さん
理由は明確ですが、獲りすぎてしまっていることが原因です。
編集部I
獲りすぎってことは、漁による影響ですか?
村岡さん
そうですね。釣り人サイドからしたら、なんとかしてくれ! というところでしょう。
しかし、獲っている漁師さん方も生活がかかっています。獲れなくなれば、獲るために時間をかけてでもやるしかないのです。
編集部I
それじゃあ、減る一方じゃないですか!
村岡さん
はい。しかし、漁師さんも自覚をしています。
午前で終わる漁が、夜通しやらなきゃ飯が食えない。釣り人も遊漁船も漁師も、“減っていることに対しての問題意識は一緒”ということです。

編集部I
それじゃあ、協力したりして……
村岡さん
おっしゃる通りです。各方面から声が上がり、会合を行ったことがあります。その際、私は釣り人の立場として参加しています。
編集部I
そんなことが!その時の内容はどんなものですか?
村岡さん
漁師・釣り人だけでなく、水産学の先生が揃い、現状の問題について話し合いましたね。
多くの案が出て、対策もいくつか挙がりました。
編集部I
じゃあ、なんとかなるのですね!
村岡さん
……すぐに何かできるわけではありません。
現状の調査をしてもらう必要もありますから、その結果を待たなければいけません。ですが、何年も待っているうちに事態は深刻になるかもしれない。自分なりに声を上げ、動いていくつもりです。
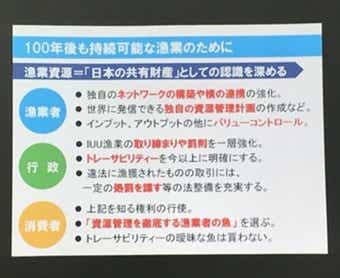
このままだと、魚がいなくなってしまう
編集部I
東京湾のスズキが減っている……非常にもどかしい思いです。話を聞いていると、他の魚にも当てはまるのではないか?と思えてきました。
村岡さん
もちろん、そうでしょうね。
今でこそ注目されていますが、マグロなんかが代表的な例でしょう。太平洋のマグロは、以前が100だったとすると……2ぐらいまで減っています。
編集部I
そんなにですか!?
村岡さん
ええ。まだ獲りますからね。このままだと“いなくなってしまう”かもしれません。

編集部I
釣り人にとってどころか、食べることすらも危うい気がするんですが……
村岡さん
ええ。ですから、さすがに沿岸漁師から獲れない・飯が食えないとの声が上がってきました。
編集部I
それは、そうですよね。
村岡さん
そうしてデモ活動へと繋がります。漁師だけでなく、釣り人までもが声を挙げはじめたのです。
資源を守るため、協力することで大きな声となり、実際に日本の漁業を見直すきっかけとなりました。
編集部I
デモ活動には、村岡さんも参加されたとお聞きしました!
村岡さん
そうですね。自分は釣り業界においては、認知をされている方だと思っています。
自分の影響力を活かして、資源回復のお手伝いを積極的に行えればというところです。
編集部I
実際行ってみて、変化は見られましたか?
村岡さん
これをきっかけに、新しい動きが見られるようにもなりました。
現状は楽観視できませんが、期待はできます。マグロの成功例が、スズキや他の魚にも繋がるように……できることはしたいですね。



