アオリイカを持ち帰る前に

座右の銘は“食べるまでが釣り”ルアー釣りからエサ釣りまで長崎県北部エリアを活動拠点とし、年中魚と遊んでいる「釣り好き!まっちゃん」です。
みなさんは釣った魚を料理していますか?
ブラックバスから海釣りへ転向した私自身も、釣れた魚の調理には困っていました。しかし、いざやってみるとこれが面白いんですよ! 自分でやることで、奥さんからも嫌な顔をされずに済みますし。
今回は釣ってよし!食べてよし! イカの王様『アオリイカ』を釣ってから下処理するまでの流れをご説明します。
アオリイカを締める

アオリイカが釣れたら、まず初めに神経締めを行いましょう。当日消費するのであれば味にそのまでの差は感じられませんが、鮮度の落ち方は大きく変わり数日後でも美味しく頂けます。
眉間をチョップして締める方を見かけますが、神経を断ち切らないと意味がありませんので、ハサミや専用アイテムの使用をオススメします。
(刃物を使用する際は、怪我等がないよう十分注意して下さい)
正しく冷やそう

鮮度を保つためのクーラーボックスと氷は必須アイテムですが、冷やし方を間違えると一気に味が落ち、本末転倒になることがあります。
そのうえで、氷を直接あてる 真水にさらすこの2点は絶対にやってはいけません! 氷に直接当てると身が白濁化し食味が一気に落ちます。
対策としてジップロック等のビニール袋にアオリイカを入れれば氷焼けを防ぎ、また墨などでクーラーボックスが汚れない一石二鳥の効果があります。
ジップロック フリーザーバッグ L
堤防に墨がついたときは
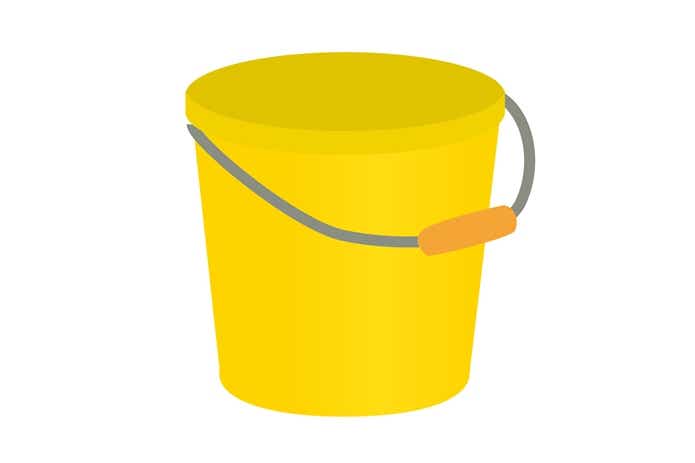
釣りを行う上で、堤防の環境維持は最低限のマナーです。堤防に墨を付けてしまったら、墨が乾く前に海水などで洗い流しましょう。
墨が原因で釣り禁止となった堤防も多数存在します。“来た時よりも美しく”の心を持ち、アングラー全員で自然環境を大切にしていきましょう。
プロックス(PROX) EVA丸水汲みバケツ オモリロープ付
捌く前に容易!時短グッズ

家に帰ったら早速捌いていきましょう。包丁を使わなくても出来る! 効率よく捌くための便利グッズもご紹介します。
調理バサミ

包丁の扱いが苦手な方に朗報。魚は包丁を使わないと捌くことが難しいですが、アオリイカを下処理する場合『調理用バサミ』一本で全行程を行うことが出来ます。
使い慣れているハサミということもあり、他魚種でもオールマイティーに活躍しますので、台所に備えておきたい便利アイテムです。
プログレード やさしい調理バサミ 缶蓋開け付き
ネギカッター

イカのお刺身でよく見かける格子状の切れ込み。旨味を出すためや醤油の乗りをよくするための隠し包丁ですが、いざやってみると面倒なものです。
そんなときは『ネギカッター』を使用してみて下さい。名前の通り、本来ネギを薄切りする調理道具ですが、イカの胴体に当てて引くだけで均等な切り込みを入れることが出来ます。
アオリイカの捌き方①:胴体の下処理

食材のメインとなる胴体部。面倒だと思われる下処理も、調理バサミを使えば簡単に行うことが出来ます。それではさっそく捌いていきましょう!
①胴と足を切り離す



調理バサミを使って胴体裏側の中央に切り込みを入れていきます。ゲソの根元付近を掴み、斜め上にめくりあげるイメージで引っ張るときれいに切り離せます。
②墨袋を取り除く※注意


内臓中央付近、光沢があるネイビーブルーの袋は、墨を充填しておく墨袋です。これを破いてしまうと台所が真っ黒になり、後処理がかなり大変。(私の家でこれをやってしまうと家族からクレームがきます)
胴と足を切り離した時点で墨袋の端を引っ張り上げ、除去しておくと大惨事を回避できます。もちろんイカスミパスタなど食材としても価値があるので、使用する場合はとっておきましょう。
③内側に残った軟骨を取り除く

胴体中央にはブレード状の透明な軟骨があります。手で簡単に取れるので引き剥がして下さい。引き剥がしたあとは胴体部の水洗いをするのですが、注意点としてゴシゴシ洗いすぎるとイカの旨味が落ちてしまします。
表面の汚れをさっと落とす程度に済ませることが美味しく頂く秘訣です。洗い終わったらキッチンペーパーなどでしっかり水気を取りましょう。
④エンペラを切り離す準備をする

胴とエンペラの接合部に指を入れ込み、エンペラの縁に沿ってスライドさせると胴との接合が取れます。
⑤皮とエンペラを引き剥がす

胴とエンペラの接合部が取れたら、胴体上部から一気に引き剥がしてください。
⑥表の薄皮を除去する

アオリイカを下処理する中で最も厄介なのが薄皮の取り除き。裏面から軽く切り込みを入れ、最初のきっかけを作り角からゆっくりと剥いでください。
難しい場合は、皮に熱湯をまんべんなく掛け氷水で冷やすと皮が柔らかくなり、キッチンペーパーや布巾などでこすり上げると簡単に除去することが出来ます。
⑦裏面の薄皮を除去する

裏面の薄皮は表面に比べ除去しやすく、キッチンペーパーや布巾でこすり、取り除いてください。加熱する場合は皮はそこまで気にならないので、そのままでもOKです。
⑧エンペラの処理を行う

皮がついた状態のエンペラは、皮と身の間に指を入れ込み横にゆっくりスライドさせるときれいに取れます。
アオリイカの捌き方②:ゲソの下処理

胴体を捌き終わったらゲソ周りの処理を行っていきましょう。ゲソだけではなく珍味と呼ばれる部位もありますので、無駄なく捌いていきましょう。
①目を取り除く


軟骨に続き、食材にはならず破棄する目の部分。目の上下にハサミを入れると簡単に取り除けます。
②ストロー・肝を切り離す

目の上にある部位は、塩辛などで使われる肝とイカが墨を吐き出すストローや漏斗と呼ばれる器官です。ストローを持ち上げ、肝袋の上からハサミを入れていくと簡単に切り離せます。
③クチバシを取り除く


ゲソの中心部には、イカの口が隠れています。口の部位はクチバシと呼ばれ珍味として重宝されています。
手で簡単に取れるクチバシですが、茶色の部分は硬いので怪我をしないように取り除いてください。
④ゲソを食べやすい大きさにカット

ゲソは食べやすい大きさにカットしましょう。またアオリイカが獲物を捕食するときに使用する触腕部は吸盤が大きいので、削ぎ落しておくと食べやすくなります。
ゲソとストローを刺身にする場合、ぬめりがあるので塩もみして、ぬめりをとると美味しく頂けます。
アオリイカ料理にチャレンジしよう

廃棄する部位がほとんどないアオリイカ。包丁のスキルも必要ないので簡単に捌くことが出来ます。この機会に料理をしない方もチャレンジしてみてはいかがでしょうか。更にエギングが楽しくなるでしょう。次回はアオリイカを使った絶品料理をご紹介します。
次回の連載記事

アオリイカの釣り方はこちらから!
釣った魚を食べるのは釣り人の特権です! アオリイカの釣り方を覚えておいしくいただきましょう。
▼必要な道具
▼ポイント選び
▼釣り方のコツ
▼季節に合わせた釣り方
▼エギングの予備知識

















