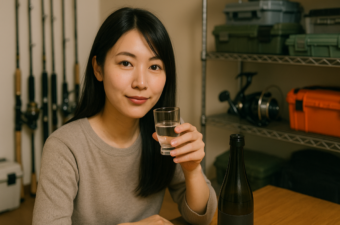給食の小魚アーモンドって、なぜあの組み合わせだったのか?

給食で出てきた、あの小魚とアーモンドの一品。
今になって思えば、なぜ小魚にアーモンドが混ざっていたのでしょうか。
噛み応えがいいわけでもないし、よく考えるとちょっと不思議ですよね。
でもじつは、あの組み合わせにはしっかりとした理由があったのです。
カルシウムを含む小魚、そしてマグネシウムを多く含むアーモンド。
この二つは、「骨づくりの黄金コンビ」だったのです。

KOBAYASHI
今回は人間にはなくてはならない栄養素、カルシウムについてのお話です。
カルシウムは「摂るだけ」ではダメ

カルシウムは、骨や歯の形成だけでなく、筋肉の収縮や神経伝達、ホルモン分泌など、体の基本的な機能を支える重要なミネラルです。
しかし、摂取したカルシウムのすべてが吸収されるわけではありません。
成人の場合、食事から摂ったカルシウムの吸収率はおよそ20〜40%程度とされています(厚生労働省『日本人の食事摂取基準(2025年版)』より)。
つまり、「カルシウムは摂っておけばOK」というわけではなく、どう吸収し、どう使われるかまでを考えることが、本当の意味での“カルシウム摂取”なのです。

KOBAYASHI
ちなみに皆さん、カルシウムは骨に多く含まれているといった認識をされていると思いますが、基本的にはその認識で間違いありません。
鍵を握るのは「マグネシウム」と「ビタミンD」

ここで登場するのが、マグネシウムとビタミンD。
マグネシウムはカルシウムを骨に固定し、筋肉や神経の興奮を抑える調整役。
現代人は加工食品の多さから、このマグネシウムが慢性的に不足しています。
ビタミンDは、腸でカルシウムを取り込みやすくする“案内役”のような存在です。
日光を浴びることで体内でも作られますが、屋内中心の生活では不足しがち。

KOBAYASHI
吸収と定着、これを動かす鍵がマグネシウムとビタミンDなのです。
ナッツ類は「マグネシウムの宝庫」

アーモンドやクルミなどのナッツには、カルシウムの相棒であるマグネシウムが豊富。
だからこそ、小魚+ナッツという給食メニューは理にかなっていたんです。
あの組み合わせは、じつはものすごく賢い栄養設計だったんですね。

KOBAYASHI
海のミネラルをたっぷり含む海藻類や干物、ミネラルバランスに優れた玄米や豆類など、ナッツ以外にもマグネシウムを含む食材はたくさんあります。
小魚には「ビタミンD」も自然に含まれているが……

ビタミンDは、日光を浴びることで体内でも生成できる栄養素ですが、じつは小魚にも多く含まれています。
なかでもサバやアジ、イワシといった青魚には、カルシウムの吸収を助けるビタミンDが豊富。
ただし、食生活の変化や屋内中心のライフスタイルによって、現代人はビタミンDが慢性的に不足しがちです。
魚を週に何度か食べていても、十分な量を確保できていないケースも少なくありません。
カルシウムを活かすには、このビタミンD不足を意識し、補うことが欠かせないのです。

KOBAYASHI
僕は毎日サプリで摂り、不足を補うようにしています。
他にもビタミンKやタンパク質なども

カルシウムの働きを支えるのは、ビタミンDやマグネシウムだけではありません。
タンパク質もまた重要なパートナーです。
体の中では、筋肉や血管、細胞膜といったあらゆる場所でカルシウムが使われており、それを受け止める“器”となるのがタンパク質です。
タンパク質が足りないと、カルシウムがうまく活かされず、全体の代謝バランスも乱れてしまいます。
そしてもうひとつの仲間がビタミンK(ほうれん草・たけのこ・さつまいも・大豆・玄米・紅茶などに多い)。
カルシウムを必要な場所に届けるための「交通整理役」として働きます。
不足すると、カルシウムが骨や筋肉ではなく、血管の壁などに沈着してしまうことも。

KOBAYASHI
つまり、カルシウムを正しく使うためには、受け皿(タンパク質)と誘導役(ビタミンK)の存在が欠かせないのです。
僕はこうしてカルシウムを摂るようにしています

僕は、よくあるパッケージの小魚アーモンドはほとんど食べません。
というのも、多くの商品が砂糖をたっぷり使って“お菓子化”しており、過剰な糖分による炎症作用が気になるからです。
……甘くて美味しいんですけどね。
ですので、いりことアーモンドをそれぞれ単品で購入し、一緒に摂るようにしています。
Amazon 素煎りアーモンド1000g

また、忙しい現代では給食のような栄養バランスを意識する機会が減りましたが、サバ缶とナッツをおつまみ的に食べるのもおすすめ。
缶詰なら保存も効くし、カルシウムだけでなく、オメガ3脂肪酸も同時に摂れる優秀な食品です。
キョクヨー さば水煮 缶詰 160g(24個)
「量」よりも「関係性」で考える

カルシウムに限らず、栄養素は基本的に単体ではなく関係性の中で働くものです。
カルシウムをどれだけ摂っても、相棒たちがいなければ意味がありません。
これは、釣りにおいても同じです。
どんなに高性能なロッドを持っていても、リールやライン、ルアーとのバランスが取れていなければ魚は釣れません。
ひとつのギアが主役のように見えても、実際はすべてが支え合って機能している。
栄養もまったく同じで、ひとつの栄養素が輝くためには、周りの仲間たちの存在が欠かせないのです。

KOBAYASHI
あの給食メニューが伝えたかったのは、もしかすると「チームプレーとバランスの大切さ」だったのかもしれません(しみじみ)。
撮影:DAISUKE KOBAYASHI