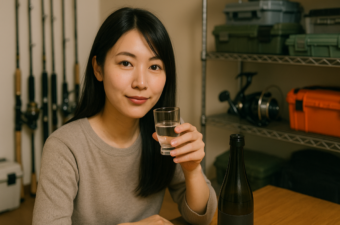魚の栄養素は“どう食べるか”で変わるんです

刺身、焼き魚、蒸し、煮つけ、唐揚げなどなど……同じ魚でも、調理の仕方によって摂れる栄養がまったく違ってくることをご存じですか?
せっかくEPAやDHAなどの良質な脂質を含んでいても、熱のかけ方ひとつで、その多くを失ってしまうこともあるのです。
魚は、調理法や食べ合わせを意識してこそ、その真価を発揮する食材です。

KOBAYASHI
今回はそんな視点から「魚の栄養をもっと上手に摂るには?」というテーマでお話ししていきます。
魚の主な栄養素を知る

魚は、人の体づくりに欠かせない栄養がぎゅっと詰まった食材です。
良質なタンパク質をはじめ、血液や脳の働きをサポートするEPA・DHA、骨の健康を保つビタミンD、カルシウムなど、現代人に不足しがちな栄養素をバランス良く含んでいます。
魚の種類によって特徴もさまざまで、青魚は脂が多くオメガ3脂肪酸が豊富、白身魚は低脂質で高タンパク、赤身魚は鉄分やタウリンが多く含まれています。
焼きすぎると脂が流れ出し、煮すぎるとミネラルが煮汁に溶けてしまうなど、調理法によって摂取できる栄養素は変化します。
調理法で摂れる栄養素が変わる

焼きすぎると脂が流れ出し、煮すぎればミネラルが煮汁に溶けてしまう——調理法によって摂取できる栄養素は変わる点にも注意が必要です。
EPAやDHAは加熱しすぎると酸化しやすく、栄養価が損なわれることも。
火加減を意識するだけで、旨味と栄養をよりしっかりと残せます。
刺身は鮮度や衛生面に気を配る必要がありますが、栄養をそのまま摂取できる理想的な調理法のひとつです。
蒸し料理は脂を落とさず、ふっくらと仕上げられるのが魅力。栄養を保ちながらヘルシーに楽しめます。
一方で、唐揚げは旨みが凝縮されて食べ応えがあるかもしれませんが、油の酸化や摂りすぎには要注意。

KOBAYASHI
大切なのはそれぞれの調理法の特徴を理解し、シーンに合わせて選ぶ知識を持つことなのです。
酸化を防ぐ工夫

魚の脂に多く含まれるEPAやDHAは、健康に良い一方で酸化しやすいという特徴があります。
酸化した脂は体内で炎症を起こす原因になることもあるため、調理や食べ方でそのリスクを減らす工夫が大切です。
焼き魚や煮魚には、レモン、生姜、大根おろしなどの抗酸化作用を持つ食材を添えるのがおすすめ。
これらは、脂の酸化を抑えるだけでなく、風味を引き立て、消化を助ける効果もあります。

KOBAYASHI
昔から親しまれてきた「サバに大根おろし」「サンマにすだち」といった組み合わせは、じつはとても理にかなった食べ方なのです。
焼きすぎには注意が必要

魚を香ばしく焼くと、見た目も香りも食欲をそそりますが、じつは“焼きすぎ”には注意が必要です。
強火で長時間魚を焼くと、「AGE(終末糖化産物)」が発生。
AGEは体内で蓄積されると、血管や肌の老化、疲れやすい体の原因になるといわれています。
焦げ目はおいしさの象徴でもありますが、食べすぎると健康面では非常にマイナスになるのです。

KOBAYASHI
そうした点で昨今、「油を使わずヘルシー」「素材のうま味を逃しにくい」などと注目を集める“蒸し料理”にも納得がいきますね。
栄養素はチームで働く

魚の栄養素は、それぞれが単独で働くのではなく、組み合わせによって効果を高め合います。
たとえば、カルシウムはビタミンDと一緒に摂ることで吸収率が上がり、鉄はビタミンCと組み合わせることで体に取り込みやすくなるのが特徴です。
また、先にも出ました魚に多く含まれるオメガ3系脂肪酸は、抗酸化作用を持つビタミンEと一緒に摂ることで酸化を防ぎ、その力をより発揮します。
魚種ごとの最適な食べ方
サバ・アジ・イワシなどの青魚

青魚は脂が多く、EPAやDHAをたっぷり含む一方で、酸化しやすい特徴があります。
できるだけ生に近い状態で食べるのが理想で、軽く火を通す程度に抑えるのがおすすめです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめの食べ方 | 刺身、しめサバ、なめろう、軽く炙った塩焼きなど |
| 組み合わせたい食材 | レモン、大根おろし、生姜などの抗酸化食材 |
| ポイント | 酸化を防ぎつつ、脂のうま味をしっかり引き出す |
タイやスズキなどの白身魚

白身魚は脂が少なく、良質なタンパク質とビタミンB群を多く含みます。
熱を加えても栄養の損失が少ないため、加熱調理との相性が抜群です。
あっさりとした味わいを活かして、素材の風味を楽しめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめの食べ方 | 蒸し魚、煮つけ、酒蒸し、塩焼きなど |
| 組み合わせたい食材 | 豆腐、小魚、きのこ類(ビタミンDとの相乗効果) |
| ポイント | やさしく火を通し、ふっくらと仕上げることでうま味と栄養を逃さず摂取できる |
マグロやカツオなどの赤身魚

赤身魚は、鉄分やタウリン、ビタミンB12が豊富で、疲労回復や貧血予防に役立つ魚です。
熱に弱い栄養が多いため、できるだけ生に近い調理法で味わうのが理想といえるでしょう。
ただし、マグロなどの大型魚には水銀が含まれることがあり、妊娠中や授乳中の方は食べすぎに注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめの食べ方 | 刺身、たたき、軽く炙ったカルパッチョ風など |
| 組み合わせたい食材 | レモン、大根おろし、トマトなどビタミンCを含む食材 |
| ポイント | 酸化や加熱による栄養損失を避け、鮮度の良い状態で適量を楽しむのがベスト |
イカやタコなどの軟体類

イカやタコは、低脂質・高たんぱくな食材で、疲労回復に役立つタウリンを多く含みます。
脂質が少ないため、ダイエット中の食事やヘルシーメニューにもぴったりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめの食べ方 | 刺身、軽いボイル、酢の物、ガーリック炒めなど |
| 組み合わせたい食材 | 酢、レモン、生姜、オリーブオイルなど |
| ポイント | 短時間でサッと加熱し、やわらかさと栄養を保つこと。消化を助ける酸味のある食材と合わせるとさらに良い |
賢く食べて、魚の栄養を最大限に活かす

魚は、種類や調理法を少し意識するだけで、同じ一皿でも体に届く栄養の量や質が大きく変わります。
焼く・煮る・蒸す・生で食べる。
それぞれに良さがあり、組み合わせ次第で健康効果を引き出すことができます。
そして面白いのは、こうした「理にかなった食べ方」は、既に昔から家庭の食卓にあったということです。
サバに大根おろし、サンマにすだち、カツオに生姜、タイの酒蒸しなど。
どれも科学的に見ても理想的な組み合わせで、昔からの知恵はじつは根拠に基づいていることが多かったのです。

KOBAYASHI
情報が簡単に手に入る昨今ですが、本質を理解することこそが何より大切だと、栄養学を学ぶ中で日々感じています。
TSURI HACK読者の皆さんには、そうした確かな情報を届けられるよう、今後も学びを深め、発信していきたいと思います。
撮影:DAISUKE KOBAYASHI